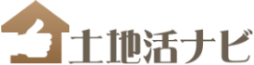「土地の一部を売却して、新しい家を建てたい」「相続税を払うために土地の一部を売りたい」といった場合、土地の分筆が必要になることがあります。
しかし、分筆に必要な手続きや注意点は、誰もが簡単に理解できるものではありません。
そこで今回は、分筆についての基本的な内容を分かりやすく解説します。また、土地の一部を売却する手順や注意点についても詳しくご紹介します。
焦ることはありません。まずは、この記事を読んで、分筆についての疑問を解消してください。そして、スムーズな土地の売却を進めましょう。
- 土地は分筆方法によって値段が違ってくる点に注意!
- 土地の一部売却には、建物解体→確定測量→分筆が必要
- マイホームの特別控除を受けるための条件に要注意!
土地を一部売却するには分筆が必要

分筆(ぶんぴつ)とは、1筆の土地を2筆以上に分けることをいいます。
「筆(ひつ)」とは土地を数える単位のことで、登記簿上でひとつの土地とされているものを指します。
ここでは、分筆とはどのようなものかについて解説します。
公図と地番、分筆について
地番とは
土地には、その土地を特定するために1筆ずつ「地番」という番号が付けられています。登記簿上は、土地の所在(市区町村および字)とともに、「●●市■■町▲▲番△△」という表記がされています。
<地番表示の例>

※「所在」「地番」「地目」「地積」と分かれていることが確認できます。
ちなみに、地番と住居表示は異なります。
住居表示は、建物を町名と街区符号および住居番号で表し、「●●市■■△丁目▲▲番○○号」というように表記されます。
一部、住居表示を実施していない地域では、現在も地番表記で対応しています。
また、住居表示は建物ごとに表記されるため、建物のない土地には付けられません。地番は法務局(登記所)が定め、住居表示番号は自治体(市区町村)が定めます。
公図とは
つぎに、土地1筆ごとの地番と形状や隣接地との位置関係を確認できる地図を公図といいます。公図は法務局で取得できます。
見た目は1つの土地に見えても、公図で確認すると複数の筆に分かれている土地はよくあります。そのため、土地を特定するためには、公図を確認することが欠かせません。
<公図の例>

この例で確認すると、赤枠で囲まれた土地は、現地で確認すると見た目では1つの土地になっており、建物が1棟建っています。
ところが、公図を確認すると、地番1-1、1-33、1-35の3筆の土地(所有者は3筆とも同じ)に分かれていることが分かります。
分筆とは
1筆の土地を2筆以上に分けることを分筆といい、それぞれ分筆登記をする必要があります。
ちなみに、複数の筆の土地を1筆の土地にすることを合筆(がっぴつ)といいます。
分筆登記が行われると、分筆された土地には新しく地番が付けられ、所有者が代われば新しい所有者の独立した土地として登記されます。
新しい地番の付け方は次のようになります。
分筆前の土地の地番に枝番がない場合
元の地番に枝番を付けて新しい地番とします。

51番の土地を2筆に分筆登記すると、「51番 → 51番1および51番2」という地番が付けられます。
分筆前の土地の地番に枝番がある場合
分筆後の1筆に元の地番を残し、他の分筆する土地には、最終枝番から順番に枝番を付けていきます。

50番2の土地を2筆に分筆登記すると、「50番2 → 50番2および50番9(最終枝番が8の場合)」という地番が付けられます。
また、公図上も分筆したとおりに新しく線が引かれ、新しい地番が記載されます。分筆登記完了後は、固定資産税も1筆ごとに課税されます。
分筆前と分筆後の公図上の変化について見てみましょう。
<分筆前の公図>

112番16の土地の地積は239.47平方メートルであり、この土地を3筆に分筆します。
<分筆後の公図>

112番16の土地が、112番16(59.84平方メートル)、112番17(59.86平方メートル)、112番18(119.82平方メートル)の3筆の土地に分筆されました。
このケースでは、112番台の土地の最終枝番は16でしたので、112番16の土地を3筆に分筆した時は、112番16(元々の地番)・112番17・112番18と、最終枝番から順番に枝番が付けられていることがわかります。
共有持分ではなく物理的に分けるには分筆
土地を分けるときに、複数の人間で共同所有するためにそれぞれの持分を登記することを共有名義といいますが、土地を物理的に分けているのではなく、土地の潜在的な権利を持分に応じて共有していることになります。
共有名義の場合、自分が持っている共有持分だけを単独で第三者に売却することは可能ですが、そのような土地は利用に制限があるので買い叩かれることは必至です。
参考 共有名義の土地を売却する方法は3つありますが、注意しなければならない点も少なくありません。詳しくは下記記事で解説しています。

分筆は土地を物理的かつ独立した所有権に分けることができます。
そのため、分筆後の土地を単独で売却することもできます。購入者は、その土地を自由に利用できるので、一定の要件を満たした分筆であれば土地の価値を下げずに売却することができるでしょう。
以下のようなケースの場合には、分筆が有効な手段となります。
- 土地を手放すことなく一部を売却する
- 土地を複数の相続人に分けて相続する
- 共有名義の土地をそれぞれの単独名義にする
- 融資を受ける場合、土地すべてでなく抵当権が設定される土地を制限する
- 相続税や固定資産税を節税する
土地を分筆する方法と注意点

では、実際に分筆する場合には、どのように土地を分けたらよいのでしょうか?
あるいは、どのようなことに気をつけたらよいのでしょうか?
ここからは、以下のような分筆に関する疑問点や注意点について解説します。
- 接道義務に注意
- 分け方によって大きく異なる土地価格
- 確定測量の方法と費用
接道義務に注意
土地上に建物を建てるためには、幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していることが必要条件です。この必要条件を接道義務といいます。
建物が建てられない土地は、その価値が大きく損なわれてしまいますので、分筆する場合は接道義務を満たすよう、土地の分け方に注意しなければなりません。
分け方によって大きく異なる土地価格

上の図で、(A)の土地を2筆に分筆する場合、(ア)(イ)(ウ)の3通りの分け方があります。
それぞれの分け方について説明します。
(ア)で分筆する場合
分筆されたどちらの土地も道路に面しているので、接道義務は満たしています。土地の価値は前面道路の路線価により決定されるので、どちらも変わりません。
ただし、分筆した土地の間口が狭すぎると、建物が建てられない可能性があるので注意しましょう。
(イ)で分筆する場合
道路から見て奥の土地は「旗竿地」と呼ばれます(敷地延長ともいいます)。
すこし利用しにくい形状に見えますが、それほど大きくない土地を分筆する場合によく採用される分筆方法です。
接道義務を満たすために、間口は2m以上取らなくてはなりません。
また、路地状部分も必ず2m以上の幅を取り、長さに応じて路地の幅が決められる場合があるので注意が必要です。
道路側の土地は間口が広いので、旗竿地より土地の価値は高くなります。
そのため、相続税や固定資産税の節税のために、このような分筆を行うことがあります。
(ウ)で分筆する場合
道路から見て奥の土地は接道義務を満たしていないため、建物を建てることができません。そのため、奥の土地は価値を大きく下げることになりますので、この分け方は採用できません。
土地を手放すことなく一部を売却したい場合には、(ア)か(イ)の分け方で分筆することとなります。
その他、二方路(角地など)、三方路(3つの道路に接している)など、土地が複数の道路に接すれば接するほど 物理的に分けやすくなります。

確定測量の方法と費用
確定測量の方法
土地を分筆する場合には、土地全体の境界が確定していなければなりません。
そのため、確定測量が行われている必要があります。
確定測量とは、すべての隣地所有者が立会いのうえで、境界(官民および民民※)の位置について確認し、境界標がなければ設置し、境界確認書に押印して確定測量図を作成します。
官民については、境界確認書ではなく道路査定図や境界確定図などの役所が発行する書類を証明書類としています。
官民とは官地(道路などの自治体や国が所有している土地)との境界を指し、民民とは私有地との境界を指します。

有効な確定測量図および境界確認書がすでに手元にあれば、確定測量を行う必要はありませんが、なければ土地家屋調査士に依頼して対応してもらいます。
土地の測量は、測量の知識が必要な測量機器などを用いて行うため、個人では対応が難しいでしょう。
そして、確定測量と同時並行で、分筆する位置に境界標を設置し、所有権などを登記します。
確定測量の費用
土地家屋調査士に確定測量を依頼した場合の費用は、一般的に30万円~40万円程度です。(土地面積30坪~40坪程度・隣地所有者3名程度・官民境界確定済の場合)
土地の大きさや隣地所有者の数により、100万円以上かかることもあるため、まずは土地家屋調査士に相談のうえ、見積りをしてもらうといいでしょう。
確定測量にかかる期間
また、隣地所有者が遠方に住んでいたり、相続が発生していたり、連絡が取れなかったりすれば完了までに時間がかかることになります。
官民が確定していない場合、官民を確定するためには道路の反対側の土地所有者の同意を取る必要があります。そのため、ある程度時間がかかると思っておいたほうがよいでしょう。
確定測量が完了するまで、数ヶ月から半年以上かかることもあります。
参考 土地を売却する際には、後々のトラブル防止のためにも、基本的には境界確定を行ったほうがよいでしょう。確定測量の方法と費用に関しては下記記事で詳しく解説しています。

土地の一部を分筆して売却する方法

ここでは、実際に土地の一部を売却した事例に基づいて説明します。
特に3,000万円の特別控除を適用するためには、次の手順で行うようにしましょう。
- 自宅を解体する
- 分筆した土地を売却する
- 新たに自宅を建築する
1.自宅を解体する
Wさん(50代・男性)は、都内の高級住宅地にある土地面積120坪の古い自宅を相続しました。そこで、相続税を納税し一部を自宅新築の資金とするために、土地の一部を売却することにしました。
<Wさんの土地分筆プラン>

Wさんは、当初Aプランで分筆し、(ア)もしくは(イ)の土地を売却しようと考えましたが、間口がそれぞれ7.5メートルと狭く、ウナギの寝床のような敷地となり、建物を建築しにくいことがわかりました。
そのため、どちらかを売却するにも売却価格が下がる可能性があります。
そこでBプランに変更し、前項で説明した旗竿地(ア)と整形地(イ)に分筆して、(イ)を売却し相続税を納税することにしました。
そして(ア)には自宅を新築して居住することとしました。
現状では、(ア)と(イ)にまたがって古い自宅が建てられていますので、まずは解体して更地とします。
2.分筆した土地を売却する
解体後に確定測量を行い、(ア)と(イ)に分筆登記を済ませたら、(イ)の土地を売却します。
(ア)を売却して(イ)を残す、という選択肢も考えられますが、旗竿地は高く売却することが難しい物件であり、(イ)の方が小さな面積で高く売却でき、パフォーマンスがよいためそちらを選択したのです。
3.新たに自宅を建築する
そして、ほどなく(イ)の売却が完了し、無事に相続税の納税が終了しました。
Wさんは(ア)の敷地に自宅を新築するプランを進め、半年後には自宅が完成しました。
こうした自宅の分筆→売却→相続税納税パターンは、相続税の改正も手伝い、増えている傾向が見られます。
マイホームの特別控除を受けるための条件に注意!

ここでは、3,000万円の特別控除を受けるために、手順以外にも気をつけなければならない点について説明します。
マイホームの特別控除とは?
売却する土地が自分で住むためのマイホームである場合、所有期間に関係なく譲渡所得※から3,000万円を控除することができます。
つまり、売却益が3,000万円までであれば、所得税や住民税は課税されません。
これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
譲渡価格(売却した価格)から取得費(購入した価格や購入時の費用など)と譲渡費用(売却した時の費用)の合計を差し引いた所得をいいます。譲渡所得には所得税と住民税が課税されます。
また、相続した不動産を売却した場合、相続した実家に住んでいなくても3,000万円の特別控除が認められています(2016年4月から2019年12月31日までの時限措置)。
ただし、居住用財産に対する特例のため、相続人が被相続人と以前に同居し、生活の拠点であったことが原則となります。
ほかにも、このような条件があります。
- 自宅のすべてを解体しなければならない
- 解体して1年以内に売買契約を結ぶ必要あり
- 解体後は貸駐車場などに利用しない
以下に、くわしく説明します。
自宅のすべてを解体しなければならない
この特例を受けるためには、現在住んでいる自宅のすべてを解体し更地で売却しなければなりません。
なぜなら、解体せずに庭の一部だけ売却したり、建物の一部だけを壊してリフォームして利用したりすると、税務署は売却した土地を居住用財産として判断しないからです。
つまり、現在住んでいる自宅をすべて解体しなければ、売却する一部の土地を含めたすべての土地が居住用財産として判断されないので、この特例を受けることができないんです。
なお、解体前には必ず見積もりを取るようにしましょう。
参考【無料】解体工事の一括見積サイト >解体して1年以内に売買契約を結ぶ必要あり
マイホームを解体した日から1年以内に売買契約を締結し、かつ、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売却することがこの特例の適用条件です。
ただし、マイホームを解体して1年以内に売買契約を締結すれば、土地の引渡しは住まなくなってから3年目の年の12月31日までに行えばよいことになります。
解体後は貸駐車場などに利用しない
建物を解体した後に、その土地を月極駐車場やコインパーキングとして貸したりすると、居住用財産と判断されなくなって、この特例を受けられなくなります。注意してください。
「もったいない」と思う気持ちはわかりますが、この特例を受けるためには更地のままにしておきましょう。
土地を分筆して一部売却するには全ての境界確定が必要
説明したとおり、土地を分筆して売却するためには、すべての境界が確定していなければなりません。まずはそこが始まりです。
確定測量には時間がかかりますので、土地の一部を分筆して売却したいと思い立ったら、まずは全体のスケジュールをよく考えましょう。
節税するためにも守るべき手順やルールがありますので、きちんと理解したうえでスケジュールに落とし込みながら、しっかり準備をしてください。
ご自身だけで不安であれば、経験豊富な不動産業者や、必要に応じて税理士や土地家屋調査士などの専門家に相談するとよいでしょう。
以上、土地の一部を分筆して売却する方法…でした。
参考 境界確定するための確定測量の方法や費用を知りたい…という方は下記記事も参考に。確定測量に必要な法務局調査や現地立会などの一連の手順や費用相場、期間などを解説しています。

不動産一括査定サービスの利用も忘れずに!
価格査定と不動産会社探しには、複数の会社にいっぺんに査定依頼できる不動産一括査定サービスが便利。今や不動産や自動車の売却には一括査定サービスを使うのが常識です。一般的な家や土地なら、大手不動産ポータルサイトのHOME4U不動産売却