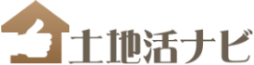「不動産をできるだけ高く売りたい」と思うのは売主として当然のことですが、売却価格に関して 、
- 売出し価格はどのように設定すればよいのだろう?
- 値下げする時はどのタイミングが効果的なのだろう?
- 値下げする前にやるべきことは何だろう?
- 値下げの幅はいくらぐらいにすればよいのだろう?
- 買主から値下げ交渉があった場合、どう対応すればよいのだろう?
といった疑問をお持ちではありませんか?
今回は、そのような方のために
- 売却価格の決め方
- 不動産を高く早く売るための価格戦略
- 不動産を高く売却するための値下げのタイミング
- 値下げする前にチェックするべきポイント
- 値下げする際の値下げのコツ
- 不動産売却における実際の値下げ事例
- 買主から値下げ交渉があった場合の対応策
などについて解説します。
この記事を参考にして、不動産を高く売却するための価格戦略や売却価格の設定方法を身に付けてください!
売却価格の決め方

査定は取引事例法による
売却価格は不動産業者による査定価格を参考にしながら、不動産業者と売主が話し合って決めていきます。
そこでまず、不動産業者が査定価格を算定する3つの方法について説明します。
土地と建物の評価を分けて考え、土地の評価は路線価を基準とし、建物の評価は再調達価格(計算上の新築価格)と耐用年数などを利用して算定します。
金融機関が担保評価を算定する方法がこの積算法です。
・収益還元法
不動産の生みだす収益性から現在の価値を算定する方法であり、主に1棟アパートや1棟マンションなどの投資用不動産の評価をする時に使われる方法です。
・取引事例法
近隣などの類似する物件の取引事例から評価する方法です。
主に実需用マンションや一戸建てなどの居住用不動産の査定に使われます。
マイホームなどの居住用不動産に関しては、近隣の似たような物件の過去の成約事例や現在の売却中物件をもとに査定します。とくにマンションなどの場合は、同じマンション内での過去の成約事例があればその成約価格を参考にして査定します。
取引事例法には机上査定と訪問査定がある
取引事例法で査定を行う場合は、机上査定と訪問査定の2種類があります。
机上査定は、不動産業者が実際に室内などを見ることなく、成約データのみをもとにおおよその査定価格を算定します。
訪問査定は、不動産業者が実際に物件に来て、室内の状況や周囲の環境、陽当りなどの個別要因を確認したうえで、より詳細に査定価格を算定します。
居住用不動産は近隣マーケットの状況など、外部要因によって査定に影響が出る可能性があるため、近く売却する予定であれば訪問査定を受けた方がいいでしょう。
売却価格は売主により異なる
過去の成約データや現在の売却中物件の価格データなどから、数字的な査定は出せますが、その裏にある売主の背景や売却理由などはわかりません。
売却価格には、それぞれの事例の売主の置かれた状況や売却理由、経済的な問題などが影響しています。
「○○のために売却する」「いつまでに売却しなければならないのか」「この価格以上で売却しなければならない」など、売主が抱える事情はさまざまです。
100人の売主がいたら、100通りの事情や背景があることでしょう。
そのため、あなたが売却価格を決める時も、不動産業者が査定した査定価格をもとにあなたの置かれた事情や銀行のローン残高、あなたの希望売却価格など具体的に相談し、価格戦略をしっかりと立てたうえで売却価格を決めましょう。
次の項では、3つの価格を設定しておく価格戦略について説明します。
前もって3つの価格を決めておく

不動産業者の査定価格をもとに、あなたの売却背景などを考慮したうえで売却価格を決定しますが、その際、「最低売却価格」「査定価格」「希望売却価格」の3つを考えましょう。
最低売却価格
この価格は「最低限この価格以上で売りたい」という価格です。
マーケット的に、ここまで下げればきっと買主が現れるだろう、という数字とリンクしなければなりません。
「この価格を満たさなければ売っても意味がない…」というケースも考えられます。
査定価格
不動産業者が「この価格であれば買主が現れるだろう」と査定した価格です。
取引事例法により算定されます。
希望売却価格
価格設定の根拠はともかく、売主として売りたいと考える希望価格です。たいていは、最低売却価格<査定価格<希望売却価格となります。
このように3つの価格を設定したうえで、価格戦略を立てて「売出し価格」を決定します。
あなたの売りたい理由や事情、売らなければならないまでの時間などを踏まえて、売り出してください 。
「少し安くても早く売りたい 」といった、どうしても売り急がなければならない状況なら、「査定価格」や「最低売却価格」を売出し価格にしなければならないでしょう。
あるいは、「時間がかかっていいので高く売りたい」ということであれば「希望売却価格」から始めることも可能です。そのために、まずは3つの価格を決めておきましょう。
売出し開始後の値下げ

売出し価格ですんなりと売却できればベストシナリオですが、価格戦略に基づき値下げをしなければならないケースも出てきます。
ここでは、売出し後に値下げをする場合の注意点などについて説明します。
販売開始から3ヶ月が目安
高く売るための適正な売却期間は3ヶ月といわれています。
その根拠は、
- 販売開始後、1ヶ月以内に反響のある購入検討者は買いの意欲が高いと考えられるので、希望売却価格で強気に勝負する
- 物件情報を公開後、情報の周知徹底が図られるのは2ヶ月後くらいである
- 情報の周知徹底後、さまざまな購入検討者から反響が来るのは3ヶ月目くらいになる
ということが挙げられます。
また、不動産業者と締結する専任媒介や専属専任媒介の期限が3ヶ月以内というのもひとつのタイミングといえるでしょう。
そのため、この期間を過ぎて売れる気配がなければ、売出し価格の改定を検討していくことになります。
なお、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介には、それぞれメリットとデメリットがあり、物件によって向き不向きがあります。詳しくは↓の記事で解説しています。

値下げ前に確認するべきこと
値下げを検討する前に 、不動産業者が「やるべきことをすべて行っているのか」ということを検証する必要があります。
チェックポイントは以下の通りです。
- 広告活動
- 物件の状態など
- 不動産業者とのコミュニケーション
広告活動について
- 大手ポータルサイト(スーモ、ホームズ、アットホーム、Yahoo不動産など)に少なくとも2つ以上、物件情報が掲載されているか
- 物件近隣へのポスティングチラシは行っているか
- 販売図面(マイソク)は写真などを使い、物件の魅力や長所をアピールできているか
- 見込客を抱えていそうな近隣の不動産業者へ物件情報を周知しているか
- レインズにも写真を掲載し、他の不動産業者が物件の魅力を認識しているか
<アピール力を感じないマイソクの例>

※このマイソクは、実際にマーケットに流通していたマイソクです。
写真や物件の長所・アピールポイントなどのコメントがなく、本当に売りたいのか疑問を感じざるを得ません。
このマイソクを見て購入意欲が高まる購入希望者はいるのでしょうか?
ちなみに、専属専任媒介(左)・専任媒介(右)という取引態様であり、おせっかいながら本当に任せておいて大丈夫なのか、心配になります。
物件の状態などについて
- 室内(特にリビングルームや水周り)は清潔な状態か?
- 照明の電球切れはないか、新しいものに交換されているか?
- ペットや家庭の臭いなどが残っていないか?
不動産業者とのコミュニケーションについて
- これまでの価格で成約しなかった理由について具体的に説明しているか?
- 競合物件の状況を聞いているか?
- 周辺のマーケットについて常に調査しているか?
- 当初の売却戦略と現状の相違点について説明できているか?
また、値下げをする時期も大切です。
不動産売買は、賃貸にくらべると 1月~3月の繁忙期の影響は少ないですが、転勤や入学などのタイミングを控えているため、やはり取引件数は増えます。
この時期に価格改定を検討しているならば、早めに対応する必要があるでしょう 。
12月は客足が鈍くなる時ですので、ここで値下げをしても効果はなく、インパクトや新鮮味が欠けてしまいますので、1月に入ってからすぐ値下げをしましょう。
また、秋は新築マンションの販売が多くなる時期ですので、物件が中古マンションの場合は9月~10月に値下げをすることも有効でしょう。
値下げの時期は慎重に検討しなければなりません。
タイミングを間違えると、マーケットへのインパクトが出せずに意味のない値下げになってしまいます。
担当者が値下げを提案してきた場合の対応について
担当者が値下げを提案してきたら、こういったタイミングや値下げの妥当性などをきちんと説明できるかどうか、確認しましょう。
売主の立場で不動産売却を考えられない不動産業者・担当者は要注意です。
不動産業者の変更が必要な理由にもなりますので、必ず確認してください。
ただし、不動産業者の変更には適切なタイミングがあります。やり方を間違えると違約金を請求される可能性もありますので、業者の変更は慎重に行わなければなりません。
下記記事では、変更するべきか否かの判断基準や変更方法などを詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

値下げ幅の考え方
値下げのポイントは3つあります。
- 値下げの幅は10%下げで
- 端数を効果的に使う
- 価格帯の変化に注意
値下げの幅は10%下げで
購入希望者は、自分の予算の+10%程度まで物件を探しています。なぜなら、住宅を購入する場合は住宅ローンを利用することが一般的で、物件価格の10%くらいがアップしたとしても、数千円のローン支払いが増えるだけだからです。
数千円のローン支払いアップで希望の物件が購入できるのであれば、購入希望者はじゅうぶん検討します。
また、1,000万円以上の物件であれば、数十万の値下げでは購入希望者の目には止まりません。
同様に、数十万円単位での小刻みな値下げも効果は上がらず、場合によっては「もう少し待てばもっと下がるかも…」と考えられてしまうため、逆効果になります。
物件価格に10%の変動があれば、既存の購入希望者は検討すべき価格と考えますし、新しい購入希望者の予算にも入るので興味を持たれる、と考えられます。
そのため、原則10%の幅で値下げを検討することが効果的です。
端数を効果的に使う
10%幅での値下げを検討したら、次は端数を調整します。
ディスカウントストアやTVショッピングなどで、「イチ・キュッ・パ(1,980円など)」や「サン・キュッ・パ(3万9,800円など)」など、端数を「8」や「9」にすると、消費者に割安感を与え、購入意欲をそそることが心理学で立証されています(「端数価格効果」といいます)。
人間の心理として、末尾に「8」や「9」がつくと安く感じるのです。
不動産の売却においても同様のことが言えます。
実際に例を挙げて確認しましょう。
<値下げの例>

百万円の単位が「8」の時は、十万円の単位を「9」とします。
これらの例を参考に、値下げの幅については不動産業者とよく相談してください。
価格帯の変化に注意
近年は、インターネットで物件を探すことが当たり前の社会となりました。
この時、購入希望者は自分自身の予算を考え、「○○○○万円以下」という検索をします。
たとえば、2,000万円以内が予算と考える購入検討者は、「2,000万円以下」で検索をするため、2,010万円の物件情報は見ていない可能性が高く、1,990万円であれば物件情報を取得して検討する可能性があります。
2,010万円と1,990万円ではたった20万円の差しかないのですが、結果は大きく違ってきてしまいます。
検索方法から500万円の単位に留意
つぎに、インターネット検索では、500万円単位で価格帯を変える検索方法が主流です。値下げのタイミングでは、この点も注意しなければなりません。
値下げを検討した価格が、3,580万円あれば3,480万円へ、2,000万円であれば1,980万円へ、と500万円の単位に気を付けて値下げしましょう。
<不動産ポータルサイトの検索画面>
※左から、ホームズ・スーモ・アットホームです。
検索用の価格帯が500万円刻みになっていることがわかります。

価格戦略と値下げの実例
次に、不動産売却における価格戦略と値下げの実際の事例を見てみましょう。
物件:中古マンション(築10年)
専有面積:70.32平方メートル・3LDK+WIC(ウォークインクローゼット)
エリア:東京23区内
売主:Mさん・30代男性(妻・子1人)
売却理由:買い替え
売却背景:現在住んでいるマンションは新築分譲で購入。妻の母親の住んでいるマンションへ引っ越したいため、買い替えを計画し売却を決意。
査定の結果、3つの価格は以下の通りとなりました。
- 最低売却価格 3,000万円
- 査定価格 3,380万円
- 希望売却価格 3,780万円
Mさんがこのマンションを新築で購入した価格は3,780万円だったので、Mさんは売出し価格を3,780万円でチャレンジしたいという強い希望を持っていました。
とはいえ、買い替えのことを考えるとあまり時間をかけることができない事情もあり、査定価格の3,380万円で売却できれば売却成功、という戦略を共有し、売出し価格を3,780万円としてスタートしました。
買い替えは一連の流れを理解し、タイミングを間違えないことが重要です。↓の記事では、不動産の買い替えを失敗しないためのポイントを解説しています。

反響は良く内覧者も多く現れましたが、さすがにこの価格では厳しく成約には至りませんでした。
その理由を「この価格では相場観とミスマッチが大きいためである」と分析し、当初の戦略通り、
3,780万円×90%=3,402万円 → 3,480万円
と値下げしたところ、1週間で成約に至りました。
値下げしたばかりのタイミングだったので、購入希望者からの値下げ交渉はありませんでした。
Mさんにとっても事前の価格戦略のシナリオ通りであり、自分自身の売りたい価格でチャレンジできたことも後悔のない売却に結びついています。
<売却時のマイソク>

※外観・エントランス・室内からの眺望の3点の写真を取り入れることで視覚的に物件の魅力を発信し、設備や環境などのアピールを十分に伝えています。
買主からの値引き交渉への対応

購入申し込みの際に買主から値引き交渉が入ることは多々あります。
むしろ、前提として考えておいた方がよいでしょう。
ここでは、買主からの値引き交渉があった場合に、どのような対応が必要なのか説明します。
値引き前に考慮するべきこと
通常、買主からの値引き交渉は買付証明書(購入申込書)の提出と同時に、不動産仲介業者を通じて行われます。その幅は、決して大きいものではないことが多いです。
たとえば、「1,850万円で端数(50万円)を切ってください」くらいの交渉です。
価格戦略の中で買主からの値引き交渉があることも想定しているため、対応に困ることはないでしょうが、確認すべきことが2つあります。
- 売却開始からの期間
- これまでの問い合わせ数や内覧者数
売却開始からの期間
売却開始から2週間で100万円値下げの買付が入ったような場合は、満額で買付が入る可能性もあるため、もうすこし様子を見た方が賢明です。
そして断り方に注意して、その購入希望者に買い上がってもらえるような交渉が必要です。
逆に、売却開始後価格改定をすることなく4ヶ月経って、100万円値下げの買付が入ったような場合は、検討の価値があると言えるでしょう。
これまでの問い合わせ数や内覧者数
これまでの問い合わせ数や内覧者数を検証しましょう。
内覧があるのに成約しない、ということは価格以外の何らかの原因があるかもしれません。
その原因を突き止めるとともに、その原因に対してデメリットとして感じない買主を待つのか、その原因を容認できるくらいの価格に値下げしたほうが有益なのかを判断しましょう。
このように、事前の価格戦略と売却開始からの期間、実際の問い合わせ件数や内覧者数などを総合的に検討し、対応するとよいでしょう。
値引きに応じる姿勢を見せつつ買主の提案を待つ
前述の通り、買主のほとんどが住宅ローンを利用するため、数十万程度の値下げが容認されないからといって、すぐに「もう買うのをやめた」とはなりません。
そのため、売主としては強気な交渉も可能ですが、せっかくの買付ですのであまりに上から目線の対応もいただけません。かといって、少しでも高く(不動産売買の場合は数十万単位です)売りたいのが、売主としての心理です。
こうした場合、値引きに応じる姿勢を見せつつ、買主がどれくらいまで買い上がれるのかを確認するとよいでしょう。
「こちらも歩み寄る姿勢を取るので、あなたも歩み寄ってほしい」という姿勢を見せて、買主がMAXでどのくらいまで出せるのかを提案してもらうのです。
それと同時に、提案された価格でのシミュレーションも行っておきます。
その価格で売却した場合に資金計画に悪影響は出ないか、引渡し条件に問題はないのか、スケジュール的には大丈夫か、などです。
「鉄は熱いうちに打て」といいますが、不動産の売却も同じです。
買主の購入熱が冷めないうちに、上手にお互いが歩み寄った価格で売却しましょう。
また、買付証明書(購入申込書)には価格のみならず、引渡し時期や決済条件に関しての希望も記載されていますので、その内容についてもよく確認しておきましょう。
- 歩み寄りの姿勢を見せる
- 買主がどれくらいまで買い上がれるのか確認する
- 提案された価格でのシミュレーションをしておく
- 買付証明書(購入申込書)の内容をよく確認しておく
用意周到な価格戦略とストーリーがカギです!
不動産を売却する時、まずは3つの価格を算定してスケジュールに落とし込み、用意周到な価格戦略を立てることがたいへん 重要です。
そのうえで、値下げ幅の設定やタイミング、買主からの値下げ交渉に対する対応などを不動産業者と相談のうえ、準備しておきましょう。
「○○○○万円で1ヶ月間売出し、成約しなければ他の要素を分析しながら、2ヶ月後には□□□□万円に値下げする」など、事前に具体的にストーリーを描いておくことが大切です。
同時にマーケットの反応を見ながら、マッチする買主を見つけていきます。
今回の記事を頭にとどめておき、信頼のできる不動産業者と相談のうえ、あなたの不動産売却を成功に導いてください。
以上、不動産を高く売却するための値下げのタイミングと値下げ幅のコツ!周到な価格戦略が成功の秘訣… でした。
参考
しっかりした価格戦略を作ってくれる不動産業者をパートナーにしたい…という方は下記記事も参考に。一括査定サイトを利用すると、複数の業者を比較できるので、より優良な業者が見つけやすくなりますよ。