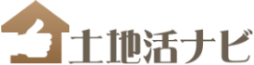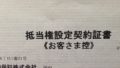「相続した不動産を売却した際、どのような税金がかかるのか知っていますか?」
相続税の他にかかる税金や、節税できる方法について知らないまま、不動産を売却すると、思わぬ出費が発生するかもしれません。しかし、そのようなリスクを回避する方法があります。
本記事では、相続した不動産を売却する際にかかる税金について解説し、節税の方法についてもご紹介します。
ぜひ、あなたが相続した不動産を売却する際に役立ててください。
譲渡所得税

土地やマンション、一戸建てなど、不動産を売却した時に譲渡益(売却益)が出れば、譲渡所得税が課税されます。高額な不動産の譲渡益(売却益)に課税されるため、税金自体も高額になる場合がありますので、注意が必要です。
不動産売却時の譲渡益にかかる税金
不動産を譲渡(売却)した時に、譲渡(売却)価格から取得費と譲渡(売却)費用を差し引いて、譲渡益(売却益)が出ればその譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。これらをまとめて「譲渡所得税」と呼んでいます。
もちろん、不動産を譲渡して譲渡益が出なければ、譲渡所得税は課税されません。
個人において譲渡所得の計算上、損失(譲渡損失)が生じた場合には、その損失の金額を他の不動産の譲渡所得の金額から控除することはできますが、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
また、相続税を納税するために相続不動産を売却した場合でも、譲渡益が出れば譲渡所得税を納税しなければなりません。
国税庁の考え方は、相続税は「相続した財産」への課税、譲渡所得税は「譲渡益(=値上がり益)」への課税という考え方であり、相続不動産でも売却した時に、その時点で実現した「譲渡益(=値上がり益)」については譲渡所得税を課税する・・・という見解なのです。
譲渡所得税の計算方法(短期譲渡と長期譲渡)
譲渡所得税は、短期譲渡所得と長期譲渡所得という2つの税率に分かれて課税されます。
短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の不動産の譲渡による所得、長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える不動産の譲渡による所得をいいます。
それぞれの税率は以下の通りとなります。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 (所有期間が5年以下) | 30.63% | 9% |
| 長期譲渡所得 (所有期間が5年超) | 15.315% | 5% |
なお、この表には平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として基準所得税額の2.1%がそれぞれ加算されています。
短期・長期いずれの譲渡所得も、上記税率にて、所得税(+復興特別所得税)および住民税が課税されることとなります。
また、譲渡所得は下記の計算式で算定します。
参考 土地や家をを売却する際にかかってくる税金に関しては下記記事で詳しく解説しています。

計算式の各項がどのようなものであるかを解説していきます。
譲渡価格
譲渡した価格ですので、いわゆる売却価格となります。
取得費
まず、その不動産の購入費用は取得費となりますが、それ以外にも取得費として加算できるものがいくつかありますので確認しましょう。
- 不動産を購入した時に不動産仲介業者へ支払った仲介手数料
- 不動産を購入した時に支払った、登録免許税、不動産取得税、印紙税
- 不動産を購入した時に支払った測量費
- 購入した不動産に賃借人がいた場合に、その賃借人を立ち退かせるために支払った立退き料
- 埋立てや盛土などの土地造成費用
- 不動産を購入し、建物等を新築するための既存建物解体費用
- 締結済の契約を解約し、その不動産を取得した場合の契約の違約金
・・・など
また、建物は古くなることにより価値が減るため、建物の購入代金相当分などから減価償却費を差し引くことになりますので、注意が必要です。
減価償却費は以下の計算式で求めることができます。
減価償却費=建物取得価格×0.9×償却率×経過年数
| 構造 | 非事業用(マイホームなど) | 事業用(賃貸マンションなど) | ||
| 耐用年数 | 償却率 | 耐用年数 | 償却率 | |
| 木造 | 33年 | 0.031 | 22年 | 0.046 |
| 軽量鉄骨 | 40年 | 0.025 | 27年 | 0.038 |
| 重量鉄骨 | 51年 | 0.020 | 34年 | 0.030 |
| 鉄筋コンクリート | 70年 | 0.015 | 47年 | 0.022 |
購入した時の売買契約書や領収書などの関係書類を保管してあれば、取得費を計算することができます。
しかし、祖父母や両親の代で購入された不動産を相続した場合、売買契約書や領収書など取得時の価格を証明するものがないケースも多くあります。
そのような時はどうしたらよいのでしょうか?
そういった場合は「概算法」といわれる計算式で、
と算定します。
例えば、親が1,000万円で購入した土地を相続し、3,000万円で売却した場合、売買契約書や領収書などの取得費を証明できる書類がなければ、取得費は5%である150万円となってしまいます。
このように概算法を採用した場合、取得費がかなり低くなってしまうため、かなりの譲渡益が出ることになり、譲渡所得の納税額も大きくなります。
そのため、購入時の売買契約書や領収書などの関係書類は、できる限り見つけることが大切です。
譲渡費用
譲渡費用とは、不動産を売却する時に発生した費用のことをいいます。
譲渡費用に該当するものは下記の通りです。
- 不動産を売却した時に不動産仲介業者へ支払った仲介手数料
- 不動産を売却した時に支払った印紙税や登録免許税
- 不動産を売却した時に支払った測量費
- 売却した不動産に賃借人がいた場合に、その賃借人を立ち退かせるために支払った立退き料
- 土地を売却するために、土地上の建物を解体した場合の既存建物解体費用
- 借地権を売却するために、地主の承諾をもらった場合の名義変更承諾料
- 締結済の契約を解約し、その不動産を取得した場合の契約の違約金
・・・など
譲渡所得税の特別控除の特例
譲渡所得にはいくつかの特例があり、要件を満たす場合は特別控除が認められています。
その種類や内容について説明していきます。
相続の申告期限から3年以内の売却
相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合、支払った相続税額(下記の計算式による)を取得費に加算できるという特例が認められています。
<取得費に加算する相続税額の計算式>
平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合

参考 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
詳しいことについては管轄する税務署や税理士などの専門家に必ず確認しましょう。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
売却した不動産が居住用財産(マイホーム)の場合は、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
つまり、売却益が3,000万円までの場合、税金はかかりません。
この特例の適用条件は、
- 相続人(子供)が被相続人(親)とともに住んでいたこと。
- また、以前に住んでいた居住用財産(マイホーム)などの場合、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
となっており、居住用財産に対する特例のため、相続人(子供)も被相続人(親)と同居し、生活の拠点であったことが原則となります。
また、居住用財産(マイホーム)を解体し、土地として売却した場合は、
- マイホームを解体した日から1年以内に売買契約を締結し、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
- マイホームを解体してから売買契約を締結した日まで、その土地を駐車場などその他の用に供していないこと。
の要件すべてに該当することが必要です。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例
被相続人(親)が地方に残した自宅を相続したが、相続人(子供)は都内で住居を持って生活しており、相続した家には住まない・・・というケースも多いのではないでしょうか。
税法のルールでは、親が住んでいた自宅に、自分が一度も住むことなく売却をした場合は、この不動産は売却した人の居住用財産ではないため、「居住用財産の3000万円の特別控除の特例」は適用できないこととなります。
しかし、すでに発生している空き家問題などを鑑みて、こういったケースでも一定の要件を満たす場合、「3,000万円の特別控除の特例 」が適用できるようになっています。
一定の要件とは、
- 相続開始直前まで、被相続人の居住用建物であったこと
- 相続開始直前まで、被相続人以外の居住者がいなかったこと
- 相続開始直前まで、被相続人居住用建物の敷地の用に供されていた土地など
- 譲渡をした人が、相続により被相続人居住用建物およびその敷地の用に供された土地などを取得した個人であること
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること(区分所有建物を除く)
- 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡であること
- 相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
- 譲渡対価の額が1億円以下であること
- 建物が耐震基準を満たしていること
などがあります。

ただし、「空き家の譲渡所得の3000万円の特別控除の特例 」と「相続税額の取得費加算の特例 」は併用できないので注意が必要です。
親が老人ホームに入居していた場合は適用されるのか?
それでは、親が老人ホームに入所してしまい、相続が発生した場合は どのような扱いになるのでしょうか。
国税庁の居住用家屋についての見解をまとめると、
- 居住用家屋とは、その者が生活の拠点として利用している家屋をいう。
- 転勤や療養などで配偶者と離れ、単身で他の場所に居住していても、いずれ戻ることが前提の場合は、居住用家屋にあたる。
- 仮住まいなどの一時的な利用のための家屋は居住用家屋にあたらない。
- 趣味、娯楽、保養のための家屋は居住用家屋にあたらない。
となります。
親が老人ホームに入所した場合、自宅は「その者が生活の拠点として利用している家屋」ではないと判断され、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例 」の適用が受けられない可能性は高いでしょう 。
住民票をそのまま自宅に残しておいたとしても、実態調査のうえ否認される場合があります。
ただし、居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円の特別控除の特例 」を適用し、自宅を3年経過後の12月末までに譲渡すれば「3,000万円の特別控除 」が受けられます。
つまり、親が生活の拠点を老人ホームに移した日より3年目の12月末までの売却が、この特例の適用を受けられる期限となりますので、親が老人ホームに入所する場合には、この特例について話し合っておくことも大切です。
自宅を解体して、土地として売却した場合には、解体した日から1年以内に売買契約を締結し、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却し、その土地を駐車場などその他の用に供していないことが適用条件となります。
しかしながら、個別要因により判断や見解が変わる可能性がありますので、詳しいことについては管轄する税務署や税理士などの専門家に必ず確認しましょう。
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の特例
相続した不動産が居住用財産であり、10年を超えて所有している場合、一定の要件を満たせば長期譲渡所得の課税の特例を受けることができます。
特例が受けられた場合は、譲渡所得税の税率が低くなります。
- 日本国内にある自分が住んでいる家屋を譲渡するか、家屋とともにその敷地を譲渡すること
- 以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること
- 譲渡した年の前年およびその前年にこの特例を受けていないこと
- 家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと、ただし、マイホームを売却した時の特別控除の特例は重ねて受けることができる。
- 親子や夫婦など特別の関係にある人に対して売ったものでないこと
・・・など
長期譲渡所得の課税の特例を受けると、譲渡所得税の税率は下記の通りとなります。
| 譲渡所得が 6,000万円以下 | 譲渡所得が6,000万円超で 6,000万円以下の部分 | 譲渡所得が6,000万円超で 6,000万円超の部分 | |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 10.21% | 10.21% | 15.315% |
| 住民税 | 4% | 4% | 5% |
| 合計 | 14.21% | 14.21% | 20.315% |
参考 国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
それでは、譲渡所得税について具体的な例でシミュレーションしてみましょう。
相続した親の自宅の売却価格 3,000万円
相続した親の自宅の購入価格 1,500万円(木造・建物価格600万円)
購入時の諸経費 100万円
売却時の諸経費 200万円
所有期間 25年(平成5年竣工・新耐震基準)
減価償却費=600万円×0.9×0.031×25=418万円
譲渡所得=3,000万円-(1,500万円-418万円+100万円+200万円)=1,618万円
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用した場合、
譲渡所得額1,618万円<3,000万円 のため、譲渡所得税は0円
譲渡所得税の節税のポイント
譲渡所得税の特例について説明しましたが、他にも譲渡所得税の節税につながるポイントについて説明します。
相続した不動産の取得時の価格を証明するものがない場合
相続した不動産が、祖父母や両親の代で購入された場合、売買契約書や領収書など取得時の価格を証明する関係書類がないケースも少なくありません 。
概算法を適用すると取得費は売却価格の5%となってしまい、かなりの譲渡益が出るため、譲渡所得の納税額も大きくなると前段で説明しました。
こういったケースでは、どうしたらよいのでしょうか?
取得時の売買契約書などの関係書類が見つからない場合、当時の物件チラシ、販売パンフレット、通帳などの出金記録、住宅ローンの金銭消費貸借契約書、登記簿謄本の抵当権設定など、購入価格を証明できそうなものがあればすべて集めておきましょう。
そして、これらの資料により取得費の実額として認められる場合がありますので、管轄する税務署に相談してみましょう。
所有期間は被相続人の取得日から計算できる
相続により取得した不動産は、原則として、被相続人(親)が取得した日を承継することができます。
そのため、相続が開始して10ヶ月以内に自宅を譲渡したとしても、短期譲渡所得にあたらず、譲渡した年の1月1日において5年を超えて自宅を所有していれば長期譲渡所得として、10年を超えて所有していれば、長期譲渡所得の課税の特例が受けられ、節税が可能となります。
確定申告の方法と時期
譲渡益が出た場合、譲渡した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納めなければなりません。
確定申告書の作成は国税庁の確定申告作成コーナーを利用して順々に数字を入力していけば、自動的に譲渡所得が計算できます。
住民税については、確定申告後に届く納付書で納めることになります。
印紙税

続いて、売買契約書に貼付する印紙税について説明します。
売買契約書にかかる税金
印紙税法で定められた課税文書に対しては、印紙税が課税されます。
課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼付することにより、印紙税を納付します。
不動産取引においては、不動産売買契約書、建築請負契約書、土地賃貸借契約書などが課税文書に該当し、契約金額によって税額が決定します。
印紙税の納付は、定められた印紙を契約書に貼付し、同じ契約書を複数作るときは1通ごとに印紙を添付しなければなりません。
また、売買代金など売主として受け取った現金に対して発行する領収書にも、印紙を貼らなくてはいけないのでしょうか?
通常は、売上代金に係る金銭の受取書に印紙税が課税されますが、一般の個人が売主となってマイホームなどの不動産を売却した場合、発行する領収書には印紙税は非課税となります。
しかし、たとえ売主が個人であっても、事業用の不動産などを売却するケースでは、印紙税がかかる場合があります。
印紙税の金額
印紙税法で定められた印紙税額は以下の表の通りです。
| 契約金額 | 軽減後の印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満のもの | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下のもの | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下のもの | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
参考 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
不動産売買契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成されるものについては軽減措置が適用されています。
なお、不動産売買契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書などについても軽減措置の対象となります。
印紙税の節税
不動産を譲渡する時、売主は売買契約書のコピーを保管しておけば差し支えありません。売買契約書原本は必要ないのです。
そのため、売買契約書原本を1通のみとして、売主は写しを買主は原本を保有する、 と取り決めれば、原本に貼付する印紙税を折半するという方法を取ることにより、売主・買主双方とも印紙税の節税を図ることができます 。
登録免許税

登録免許税は、主に土地や建物を購入したり建築したりした時、所有権保存登記や所有権移転登記等などを行う際に課税されます。
これらの登録免許税は、不動産取引上、買主が負担しますが、売主として負担するべき登録免許税はどのようなものでしょうか。
住宅ローンが残っている場合の抹消登記など
まず、不動産を相続し相続登記を行う際、所有権移転に伴って登録免許税が課税されます。
そして、相続不動産に金融機関などの住宅ローンの抵当権が登記されている場合、相続不動産の 売却代金から残債を返済し、抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権抹消登記にも登録免許税が課税されます。
参考 抵当権抹消登記なしに引き渡すと、違約金や損害賠償を請求される可能性もありますので、ご注意ください。抵当権に関しては、下記記事で詳しく解説しています。

また、所有者の登記簿謄本上の住所と現住所が相違している場合、住所変更登記を行う必要があり登録免許税が課税されます。
登録免許税の金額
相続登記の際の、所有権移転登記に伴う登録免許税は、「固定資産税評価額×0.4%」という計算式で算定されます。
売買の場合の登録免許税は「固定資産税評価額×1.5%(軽減措置あり)」ですから、相続の場合はかなり割安となります。
固定資産税評価額は、市区町村の役所窓口などで取得できる「固定資産評価証明書」に記載されています。
また、抵当権抹消に関する登録免許税の計算方法は、不動産1個につき1,000円となっています。
不動産が一戸建などの場合は、土地と建物を1個ずつとして計算しますが、土地が何筆かに分かれているような場合は、1筆1個として計算しますので、注意しましょう。
土地2筆 建物1棟 → 登録免許税 計3,000円
一戸建ての場合もマンションの場合も、見た目が一団の土地であっても、登記上は数筆の土地に分かれている場合があります。
土地が数筆に分かれている場合は、その分登録免許税が増えることになります。
なお、住所変更登記にかかる登録免許税も不動産1個につき1,000円となります。
節税だけにこだわってはいけません
親の自宅などを相続して売却した場合に、相続税以外にかかる税金や節税方法について説明してきました。
さまざまな特例などについても紹介しましたが、「売却する」と意思決定したら、早く行動に移すことで節税につながるケースがあります。
どういった方策が自身のケースでは得策なのか、税理士などの専門家の知恵や知識を利用しながらベストな道を探しましょう。
しかし、不動産の売却に成功するためには、タイミングも重要な要素です。
節税テクニックにこだわるあまりに、売却できるタイミングを逃しては本末転倒です。
地方にある親の自宅などの不動産は、マーケットが小さくニーズが限られる場合もあり、せっかくの商談のチャンスを逃すと売却できなくなる可能性があります。
空き家などを放置し続けることは、各種のコストやリスクが生じる負債の「負動産」となってしまうので、売れるうちに売ることを念頭に置きましょう。
参考 空家等対策特別措置法について、詳しくは下記記事で解説しています。行政処分の対象となる「特定空家等」に当てはまらないかどうか、確認しておきましょう。

そして、あなたの相続不動産の売却を成功させてください。
以上、相続した不動産(マンション・一戸建て・土地・空き家)を売却した際にかかる税金について知っておくべきこと…でした。
参考 不動産売却時にかかってくる税金の節税ノウハウも知りたい…という方は下記記事も参考に。とくにマイホームの売却にはさまざま節税ノウハウがあります。知っておかないと損しますよ。
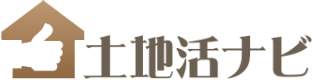
不動産一括査定サービスの利用も忘れずに!
価格査定と不動産会社探しには、複数の会社にいっぺんに査定依頼できる不動産一括査定サービスが便利。今や不動産や自動車の売却には一括査定サービスを使うのが常識です。一般的な家や土地なら、大手不動産ポータルサイトのHOME4U不動産売却