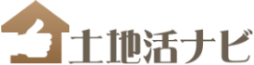空き家を所有している方にとって、「固定資産税が6倍になる可能性がある」と知ったら、心配になりますよね。
しかし、空き家問題を解決するために全国的に取り組みが進められているのをご存知ですか?
平成27年5月から「空家等対策の推進に関する特別措置法」(略して空家等対策特別措置法)という法律が施行され、自治体は空き家問題に積極的に対処できるようになりました。
この法律がどのように機能するのか、そして行政指導や行政処分に至るまでの流れについて、詳しく解説します。
空き家を所有している方必見の情報です。ぜひ、最後までお読みください。
「空家等対策特別措置法」が施行された背景と目的

空き家の現状と将来予測
5年ごとに行われる総務省の「住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家の総数は、
平成10年・約576万4,000戸、
平成15年・約659万3,000戸、
平成20年・約756万7,000戸、
平成25年・約819万6,000戸
平成30年・約840万6,000戸
と増え続けており、総住宅数に占める空き家の割合である空き家率も平成30年に13.6%と過去最高を記録しました。
空き家率が最も高いのは、和歌山県の18.8%で、次いで徳島県が18.6%、鹿児島県が18.4%、高知県が18.3%,愛媛県が17.5%となっており、比較的空き家率が低い東京都でも10.4%も占めています。
このうち、管理の不適切な空き家が、衛生上の問題、防災・防犯上の問題、景観悪化の問題などの社会的な問題を日本全国で引き起こしていました。
そのため、強制力を持った対策の必要性が議論され、平成26年11月に空家等対策特別措置法が衆議院にて成立されたのです。
空き家の将来予測として、民間のシンクタンクである野村総合研究所は、既存住宅の除却や住宅用途以外への利活用が進まない場合、2033年の空き家数は約2,150万戸、空き家率は30.2%にいずれも上昇すると予測しています。
住宅3軒につき1軒が空き家・・・という日が来るかもしれません。

※引用元:株式会社野村総合研究所「2018年、2023年、2028年および2033年における日本の総住宅数・空き家数・空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)の予測」
空き家が放置される理由
空き家を放置したままでは様々なリスクが発生し、近隣住民などから損害賠償請求などの深刻な事態に発展することも考えられますが、多くの人は空き家をそのままにしています。
リスクがあるとわかっていても放置してしまう理由とは何なのでしょうか。その理由としては、このようなものがあります。
- 更地にすると住宅用地の特例が受けられなくなる
- 相続でもめている
- 権利調整がつかない
- 希望価格で売却できない
- 所有者不明の状態である
それぞれについて、以下に詳しく解説します。。
更地にすると住宅用地の特例が受けられなくなる
自宅や賃貸アパートなどとして利用されている住宅用地は、住宅用地の特例により固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられます。
しかし、自宅などを解体して更地にしてしまうとこの軽減措置は受けられなくなり、固定資産税・都市計画税の算定根拠となる課税標準額が跳ね上ってしまうのです。
特に小規模宅地(住宅用地で200平方メートルまでの部分)については、更地にすると固定資産税の課税標準額が6倍になります。
<住宅用地の特例による軽減措置>
| 区分 | 区分詳細 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|---|
| 更地 | 自宅や賃貸アパートなどの建物なし | 課税標準額×1.4% | 課税標準額×0.3% |
| 小規模宅地 | 住宅用地で住戸1戸につき200㎡までの部分 | 課税標準額×1/6×1.4% | 課税標準額×1/3×0.3% |
| 一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地(200㎡を超えた部分) | 課税標準額×1/3×1.4% | 課税標準額×2/3×0.3% |
そのため、誰も使用していない建物であっても、そのまま残しておけば住宅用地の特例により固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられるため、建物の解体や除却が進まず、空き家として放置されることになります。
空き家のまま放置される理由としては、この理由が一番多いと考えられています。
具体的な例で見てみましょう。
(更地の場合の固定資産税)3,000万円×1.4%=42万円
(空き家がある場合の固定資産税)3,000万円×1/6×1.4%=7万円
上記の場合、差額は35万円となり、空き家がある場合とない場合では大きな違いが生まれます。
ちなみに、老朽化した空き家であれば建物の評価額は極めてゼロに近くなりますので、建物に対する固定資産税はほとんどかかっていないと考えられます。
相続でもめている
相続人が複数存在し、遺産分割や不動産の処分方法などについて相続人の間で足並みがそろわない場合です。この場合も、相続人の間で意見の調整ができるまで相続不動産に手を付けられないため、放置されることとなります。
権利調整がつかない
複数の人で一つの不動産を共有名義として所有している場合や土地の所有者と建物の所有者が違う場合など、権利関係が複雑なケースもあります。
このような場合も、売却や利活用の方法について意見が食い違い、放置せざるをえない状況になることがあります。
希望価格で売却できない
解体費用が捻出できないため古家付き売地として売りに出したが、住宅需要がないというケースや建築の要件を満たしていない土地のため売れないケースなど、売却活動で行き詰っている場合、そのまま放置されることがあります。
所有者不明の状態である
空き家の所有者が亡くなり相続人がいない場合や、相続人がいても全員が相続放棄をした場合など、実質的な不動産所有者が不明なケースです。
最終的には代執行などを行い国庫に帰属させることになりますが、それまでは放置された状態が続いてしまいます。
空家等対策特別措置法の目的
空き家が放置されてしまうさまざまな理由はわかりました。
では、空き家を放置したままでいると、どのような問題が発生するリスクがあるのでしょうか。
まず、起こりうるリスクについては、このようなものが挙げられます。
- 家屋の老朽化による倒壊リスク
- 衛生上の有害リスク
- 景観悪化のリスク
- 不審者などによる治安悪化リスク
- 火災などの防災リスク
それぞれについて、具体的に見ていきましょう。
家屋の老朽化による倒壊リスク
日本の住宅は木造建築が多いため、適切なメンテナンスを行わないと、老朽化による腐食などで構造的に弱くなります。
その状態で放置すると、地震や台風などで倒壊してしまうリスクがあります。
衛生上の有害リスク
空き家への不法投棄やゴミの放置などにより悪臭が発生し、害虫や害獣の発生にもつながるため、周辺住民に迷惑をかけることになります。
景観悪化のリスク
外壁に落書きをされたり、庭木が繁茂して建物を覆い隠してしまうなど、治安の悪化や周囲との景観悪化につながるリスクがあります。
不審者などによる治安悪化リスク
景観悪化のリスクにより、外部から見えにくい状態になると、空き家ということもあり不審者が侵入するリスクが高まります。
それにより、重大な犯罪や放火などの深刻な事態に発展するリスクがあるのです。
火災などの防災リスク
ゴミの放置や不審者の侵入などにより、放火による火災のリスクや、積雪・落雷などによる倒壊・火災リスクなどが高くなります。
これらのリスクに起因して、倒壊による隣家被害や避難経路遮断、火災による周辺住居への延焼などが発生した場合、所有者への損害賠償請求といったケースも想定されます。
こういった事態を招かないために、空家等対策特別措置法が施行されています。
空家等対策特別措置法の第1条に、その目的が規定されています。
(目的)
第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
わかりやすく言うと、「適切に管理されていない空き家を放置すると、防災、衛生、景観などの面で周囲の住民にも迷惑をかけるので、そういった事態を招かないよう空き家の管理・運営についてきちんと決めましょう」ということになります。
空家等対策特別措置法における「空き家」の定義

空家等対策特別措置法では、「空家等」と「特定空家等」を定義しています。
ここでは、それぞれどういった判断基準で判定されるのか説明します。
「空家等」とは?
空家等対策特別措置法に定める「空家等」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを言います。
具体的には、以下の5つのポイントと年間を通して利用されているかどうかを含めて、客観的に空き家か否かを判断されます。
- 建築物の用途や状況
- 人の出入りの有無
- 電気、ガス、水道などライフラインの使用状況
- 所有者の登記や住民票の内容
- 管理の状態
それぞれについて、以下に詳しく見ていきましょう。
建築物の用途や状況
建築物の用途が賃貸用、売却用、自己利用など明確な場合は問題になりませんが、特に何の用途にも供していない場合は、管理が疎かになりがちなので 注意が必要です。
例として、郵便受けにチラシが溜まっていないか、窓ガラスが割れたままで放置されていないか、夜になると灯りが点いているか、ゴミが不法投棄されていないか、などが判断基準となります。
人の出入りの有無
年間を通した人の出入りの有無により、その建築物が利用されているかどうかを判断します。
電気、ガス、水道などライフラインの使用状況
人が生活を送るうえで必要な電気、ガス、水道などのライフラインの使用状況により、その建築物が利用されているかどうかを判断します。
所有者の登記や住民票の内容
相続などで不動産の所有者が代わった時は所有権移転登記、所有者の住所が変わった時は住所変更登記など、登記は不動産を管理するために必要なものです。
また、住民票の内容とも整合性が必要となります。
登記内容や住民票との整合性に不備がある場合は、空き家と判断される可能性があります。
管理の状態
その建築物が防災・防犯面、衛生面、景観などの面において問題ない状態か否かが判断されます。管理の状態は、特定空家等の判断に直結するポイントでもあるため、特に注意が必要です。
いかがでしょうか?
「常態化」の期間の基準は「1年間」ということになります。
つまり「所有者が住むわけでなく、他人に貸すわけでもない状態が1年間続き、管理も不適切な場合、空き家と判定される可能性が高い」ということになります。
しかし、自治体などは所有者からの聞き取り調査も行いますので、何らかの利用の実態があればその場で申告しましょう。
「特定空家等」とは?
空家等対策特別措置法に定める「特定空家等」とは、「空家等」の中でも以下の状態にあると認められる空き家を言います。
そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 基礎の不同沈下や柱の傾きなどにより、建築物が著しく傾斜している。
- 基礎や柱部分に破損や変形が生じている。
- 屋根や外壁などが脱落、落下する恐れがある。
など、保安上のリスクがある状態を言います。
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 不法投棄などによるゴミの放置で悪臭が発生している。
- ネズミやハエなどの害獣・害虫の大量発生している。
- アスベストなどの飛散による健康被害の危険性がある。
など、衛生上または健康上有害と思われる事態が起き、周囲に影響を及ぼすリスクがある状態を言います。
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 外壁などに落書きがされたままになっている。
- 庭の樹木などが繁茂して建築物を覆い隠している。
- 窓ガラスが多数割られている。
- 門扉が施錠されていない。
など、不特定多数の第三者が容易に侵入できることにより、防犯上の問題に発展するリスクがある状態を言います。
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
- 庭の樹木が隣家や道路などに大幅に越境している。
- 猫などが住みついてしまい鳴き声やフン害など周囲に迷惑をかけている。
など、周囲の住民に生活上の迷惑をかけるリスクがある状態を言います。
つまり空き家の中でも、そのまま放置していると、
- 倒壊などの保安上のリスク
- 衛生上または健康上有害となるリスク
- 著しく景観を損なっているゆえの防犯上のリスク
- 周囲へ生活上の迷惑を及ぼすリスク
などがある場合は、「特定空家等」に指定されることになりますので、注意しましょう。
空家等対策特別措置法による行政対応の流れ

空家等対策特別措置法が施行されたことで、自治体など行政側の対応はどのように変わったのでしょうか?
具体的には、このような対応ができるようになりました。
- 自治体による立入調査が可能に
- 所有者特定のため固定資産税台帳の利用などが可能に
- 適正管理の助言→指導→勧告→命令→代執行
- 「特定空家等+勧告」で固定資産税の軽減措置対象外に!
- 命令に従わなければ50万円以下の罰金も
- それでも改善がみられなければ代執行へ
それぞれについて、以下に詳しく解説します。
自治体による立入調査が可能に
たとえ空き家とはいえ、所有者に無断で敷地内に入ることは不法侵入罪に問われる可能性もあるため、これまでは危険性が認められていても立ち入ることが難しい状況でした。
しかし、空家等対策特別措置法の施行後は、管理が適切でない空き家の場合、外観目視による調査では不十分なケースでは、所有者へ事前通知のうえ、自治体などが敷地内への立入調査を行うことができるようになりました。
立入調査を行うことにより、空き家等のより詳細な状態の把握や具体的な対応策の検討が可能となります。
また、所有者は正当な理由なく立入調査を拒否すれば、最大20万円以下の過料が科される可能性があります。
所有者特定のため固定資産税台帳の利用などが可能に
空き家の立入調査を行うためには、事前に所有者へ通知しなければなりません。
そのため、次のような方法で所有者調査を行い、所有者の特定をします。
- 不動産登記情報による登記名義人の確認
- 住民票、戸籍謄本などによる登記名義人や相続人の存否および所在の確認など
- 固定資産税台帳の内部利用
- 電気・ガス・水道の使用状況についての照会
- 必要に応じて地域住民への聞き取り調査など
適正管理の助言→指導→勧告→命令→代執行
現地立入調査や所有者調査を経て、特定空家等と判定された場合、自治体が除却や修繕、樹木の伐採など適正な管理の助言や指導などをすることができます。
そのうえで、改善されない場合は勧告し、正当な理由なく勧告に係る措置を取らない場合は命令し、さらにそれでも措置を取らなければ代執行することとなります。
「特定空家等+勧告」で固定資産税の軽減措置対象外に!
特定空家等と判定されたら、早急に自治体の助言や指導に従いましょう。
それにより、改善が認められれば特定空家等から除外されます。
しかし、助言や指導を受けたにもかかわらず、そのまま放置すれば勧告を受けることになり、固定資産税の住宅用地の特例による固定資産税・都市計画税の軽減措置の適用対象外となりますので注意しましょう。
参考 固定資産税の計算方法や特例に関しては、こちらの記事が詳しいです。

命令に従わなければ50万円以下の罰金も
勧告を受けたにもかかわらず放置を続けた場合、自治体は建物などの解体や除却、修繕などの命令を行います。
命令は、助言・指導・勧告などの行政指導と違い、行政処分にあたる重い処置であり、命令に反した場合は50万円以下の罰金が科されます。
それでも改善がみられなければ代執行へ
命令を受けても空き家に改善が見られない場合、自治体が所有者に代わり、建物などの解体や塀や樹木の撤去などを行う代執行が行われます。
もちろん、かかった費用は所有者の負担となります。
費用負担を拒否した場合は、所有者の財産の差押えを受けることもありますので、注意が必要です。
<空家等対策特別措置法による行政対応フロー>

空家等対策特別措置法施行後の行政の対応フローについて見てきました。
空き家を放置し続けると、建物の倒壊や火災の発生、周辺への生活環境破壊など近隣住民に対して、甚大な迷惑や被害を及ぼす危険性があるため、時間的な猶予はありません。
自治体などから管理状況の改善などの行政指導を受けたら、迅速に対応し、行政処分に発展することのないよう心がけましょう。
解体に助成金や税金減免のある自治体も

空き家を解体するにも、多額の工事費がかかります。費用を考えると、ついつい後回しになってしまう・・・というケースも多いのではないでしょうか。
解体工事の坪当たり単価の相場はこちらを参考にしてください。
<解体工事の費用相場>
| 構造 | 坪当たりの単価 |
|---|---|
| 木造 | 3万円~4万円 |
| 鉄骨造 | 4万円~5万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 5万円~8万円 |
解体工事の費用相場は 万円 〜 万円です。
しかし、空き家の解体工事費用については自治体から補助金が交付されることも多く、中には固定資産税の減免を行っている自治体もあります。
解体工事の補助金交付を受けたり、固定資産税の減免を受けたりするためには、一定の条件があります。自治体によってそれぞれ規定されているため、事前に各自治体に問い合わせて確認しましょう。
解体工事に着手してしまった後では、補助金の申請ができないケースも多いので注意してください 。
また、気をつけなければならないのは、補助金などは解体工事を完了した後に支払われるということです。つまり、いったんはご自身で工事費全額を解体業者へ支払い、その後に申請をし、認められれば交付を受けることができます。
いずれにしても、補助金などの制度を利用することにより、空き家が不適切な状態であれば一刻も早くを解消するよう動きましょう。
空家等対策特別措置法の本当の意義
空き家問題に悩んでいる人にとって、空家等対策特別措置法が施行されたことは厄介なことと感じるかもしれませんが、それは間違いです。
空家等対策特別措置法という法律が制定されたことで、自治体などが積極的に空き家問題に着手できることになり、悩みを持つ所有者へアドバイスや協力ができるようになったのです。
空き家問題に取り組むNPO法人も設立され、各自治体とのタイアップや連携、民間業者とのネットワーク構築など、空き家問題を解決するための環境はどんどん整ってきています。
そのため、空き家問題に悩みを持つ所有者はこういった環境を最大限利用し、空き家の利活用、適切な管理、解体後の売却など、さまざまな空き家の対策を進めることが大切です。
今後は、自治体などがさらに踏み込んだ空き家の利活用事業に乗り出し、空き家問題の解決が地方創生とともに相乗効果を発揮することが期待されています。
以上、空家等対策特別措置法(空家法)とは?固定資産税が6倍に?罰金の可能性もあり!… でした。
参考
古家付き土地をどうやって売ったらいいのか知りたい…という方は下記記事も参考に。古家付きの土地は3つの売却方法があります。それぞれのメリットやデメリットなど、詳しく解説しています。

不動産一括査定サービスの利用も忘れずに!
価格査定と不動産会社探しには、複数の会社にいっぺんに査定依頼できる不動産一括査定サービスが便利。今や不動産や自動車の売却には一括査定サービスを使うのが常識です。一般的な家や土地なら、大手不動産ポータルサイトのHOME4U不動産売却