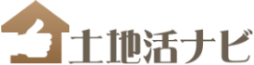「相続した家があるけど、いっそのこと解体して更地で売った方がいいのだろうか?それとも、そのままで売った方がいいのかな?」
古家が建っている土地を売るときには、解体して土地だけの状態にすべきかどうか悩ましいところですよね…。
住宅として価値があるならともかく、倒壊寸前で住めないような家を欲しい買主はなかなか見つからないでしょう。かといって、更地にするには解体コストがかかりますし、一度取り壊してしまうと元には戻せません。
今回は、売却の際に家を解体して更地にする8つのメリットと7つのデメリットを解説し、状況別の選択肢もご提案します。この記事を読めば、古家を解体して更地にしてから売るべきか悩んだときに「損をしない判断」ができるようになるでしょう。
売却の際に家を解体して更地(土地だけ)にするメリット

まずは、家を解体し更地として売却するメリットを説明します。
- 買い手を見つけやすい
- 高値で売りやすくなる
- 建物の契約不適合責任を負わない
- 地中埋設物などを確認できる
- 解体費用は譲渡所得の経費として認められ節税できる
- 管理コストがかからない
- 「特定空き家」に指定されるリスクもなくなる
- 近隣からの苦情や損害賠償請求に対応する必要がない
それぞれについて、以下に詳しく解説します。
買い手を見つけやすい
一般的に、使いみちのない家が建っている土地より更地の方が買い手を見つけやすいものです。買い手が古家を使わない場合、買取後に自費で解体しなければなりません。それよりは更地の方が使い勝手がよく解体の手間も省けます。
買い手にとっては解体費用を負担する必要がなく経済的メリットがあるうえに、建物の建築にすぐに着手できるという時間的メリットも得られます。
更地は見た目もすっきりしているため、買い手に好印象を与えます。
倒壊寸前の古家が建っている場合などには、自主的に解体してから売るようおすすめします。
<古家解体の例>

高値で売りやすくなる
古家が建った土地を希望する買い手は「購入後に自分で解体して建て替えよう」と考えているケースが多数です。その場合、買い手は、解体費用がかかることを想定して価格交渉するため、売却価額から解体費用分を差し引くよう要求してきます。
買い手によっては実際の解体費用以上に値下げを要求してくるケースも多く「買い手主導」の価格交渉となって売り手には不利な取引になりがちです。
更地であれば解体費用はかからないので、売り手にとって不利になる交渉材料はありません。
解体費用分の差し引きを考慮する必要がなく、むしろ「売り手が負担した解体費用」を考慮するよう求める交渉もできて、有利に取引を進めやすくなります。
更地で売却すると売り手主導の取引になりやすく、高値で売却しやすくなるメリットがあるといえます。
建物の契約不適合責任を負わない
建物つきの土地を売ると「契約不適合責任」を負う可能性があります。契約不適合責任とは、売買の対象物が契約の目的に合致していないときに売主が負う責任です。
約束と違うものを売ると、修繕や代替物の引き渡し、代金減額や損害賠償請求、契約解除などをされるリスクが発生します。
古家のような老朽化した建物の場合、売却後にどのような欠陥や不具合が出てくるか予想もつきません。予想外に高額な賠償請求をされては大変です。
たしかに交渉次第で契約不適合責任を免責とすることも可能ですが、相手が納得しない可能性もあります。はじめから建物を解体しておけば、契約不適合責任のリスクをゼロにできるメリットがあるでしょう。
地中埋設物などを確認できる
地中には、杭、ガラ、埋設管などの埋設物が埋まっていることがあります。産業廃棄物や汚染物質を含んだものが埋められている可能性も否定できません。
買い手への決済引渡し後にこのような地中埋設物が確認されると、契約不適合責任を追及されることになり、ケースによっては損害賠償請求や契約解除をされる可能性もあります。
事前に家を解体すれば地中埋設物も確認できるので、契約後のトラブルを未然に防げるメリットがあります。
解体費用は譲渡所得の経費として認められ節税できる
不動産を売却すると「譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。譲渡所得税は、不動産の売却によって得られた利益である「譲渡所得」にかかる税金です。譲渡所得税が発生すると住民税もかかります。
譲渡所得計算の際には、不動産の売却価額から取得費用(購入費用)と譲渡費用(売却にかかった経費)を差し引けます。
売却にかかった経費が高額になれば差し引ける金額が大きくなり、多少利益が出ても譲渡所得税や住民税はかからない可能性が高まります。
更地として売却するために行った解体工事の費用も、譲渡のための経費と認められるので、売却価格から差し引くことができます。
解体のタイミングに要注意
ただし「経費」として認められるには、売却が現実的になってから解体に着手しなければなりません。
「買い手に譲渡するために必要」な解体費用でなければ、経費として認められないのです。
まだ買い手もまったく見つからないうちに自己判断で解体すると「譲渡のための経費」と認められないので、解体工事を行うタイミングは慎重に判断しなければなりません。売買契約書の中に解体費用負担に関する条件を加えておくと、エビデンスとなります。
管理コストがかからない
古家が建っていると、管理コストがかかります。人の住んでいない家はどんどん傷んでいくので、ときおり掃除や空気の入れ替えなどをしなければならず、害虫や害獣駆除も必要となるでしょう。
建物管理業者に依頼することもできますが、費用がかかってしまいます。
しかし、解体してしまえば、そのような管理のための労力や費用も必要ありません。
ただし雑草が増えすぎたり不法投棄物が投げ込まれたりすると、土地の見た目が悪くなって売れにくくなる可能性もあります。最低限の管理は行いましょう。
「特定空き家」に指定されるリスクもなくなる
平成27年5月から空き家等対策特別措置法が全面施行され、空き家の不適切な管理状況を改善するために各自治体が厳格に対応しています。
老朽化して倒壊のおそれや周囲に悪影響を及ぼす可能性のある建物を放置していると、自治体から「特定空き家」と指定される可能性があります。
特定空き家になると、状況を改善するために助言・指導や勧告が行われ、それでも従わないと「改善命令」が下されます。無視していると空き家を強制撤去されて費用負担を求められたり、50万円以下の罰金という刑事罰が科されたりする可能性もあります。
建物を自主的に解体すると特定空き家に指定されるリスクも自治体から指導を受ける可能性もなくなるので、メリットがあるでしょう。
空き家等対策特別措置法について、詳しくは下記記事で解説しています。行政処分の対象となる「特定空き家等」に当てはまらないかどうか、確認しておきましょう。

近隣からの苦情や賠償請求に対応する必要がない
古家が建っていると、倒壊の危険が生じたり害虫、害獣が発生したりして周辺の環境を悪化させる可能性があります。
周辺住民から苦情が来て対応が必要になるケースも多いですし、ときには屋根や壁が崩れて周辺住民にケガをさせて、損害賠償請求される可能性もあります。そのようなリスクの高い物件は買い手にも敬遠されてしまうでしょう。
家を解体すると近隣からの苦情や損害賠償請求を受けるリスクはほとんどなくなり、メリットを得られます。
なお土地に不法投棄物が投げ込まれたりゴミを置かれたりすると、やはり周辺環境を悪化させてしまいます。更地にした後も最低限の管理は行いましょう。
売却の際に家を解体して更地(土地だけ)にするデメリット

次に、更地にした場合のデメリットについても説明します。
- 解体費用がかかる
- 建物滅失登記の手間と費用がかかる
- 年をまたぐと固定資産税・都市計画税が高くなる
- 再建築不可物件だと建物を新築できない
- 既存不適格物件の場合、建て替えに制限がかかる
- 買い手が住宅ローン、住宅ローン減税を受けられない可能性がある
- 古家を希望する買主を逃してしまう
それぞれについて、以下に詳しく解説します。
解体費用がかかる
土地を更地にするためには、自己負担で解体工事を行わなければなりません。
解体工事の費用は、木造の場合、目安として@3万円~4万円/坪程度で、一戸建てを解体する場合でも100万円以上かかるケースもよくあります。
高額な解体費用を負担しても、必ずしも土地値に上乗せできるとは限りません。経済的にデメリットが生じる可能性があります。
解体工事の坪当たり単価は建物の構造によっても異なります。相場はこちらを参考にしてください。
<解体工事の費用相場>
| 構造 | 坪当たりの単価 |
|---|---|
| 木造 | 3万円~4万円 |
| 鉄骨造 | 4万円~5万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 5万円~8万円 |
解体工事の費用相場は 万円 〜 万円です。
解体工事費は、売却代金が得られる前に支払う必要があるため、事前に見積り書をもらい、資金計画をきちんと立てておきましょう。
参考【無料】解体工事の一括見積サイト >
<解体工事の見積り事例>

見積書の見方
この事例の場合、木造2階建・延床面積167平方メートルの建物解体工事に対する見積り額が165万円ですので、坪単価は
165万円÷167平方メートル×3.3058=@32,662円/坪
となります。
建物滅失登記の手間と費用がかかる
建物を解体したら、工事の終了と同時に建物滅失登記の申請をしなければなりません。
建物滅失登記とは「建物がなくなった」ことを不動産の全部事項証明書に記載してもらうための登記です。
建物滅失登記には期限があり「建物解体後1ヶ月以内」に建物の所在地を管轄する法務局へ申請しなければなりません。遅れると「10万円以下の罰金」が科される可能性があるため、必ず早めに申請しましょう。
土地家屋調査士へ依頼できますが、依頼すると土地家屋調査士の費用も発生します。目安は4~5万円程度です。
それほど難しい手続きではないため、自分自身で行って費用を節約することも可能ですが労力がかかります。
建物滅失登記の具体的な方法に関しては、下記記事で詳しく解説しています。

年をまたぐと固定資産税・都市計画税が高くなる
自宅などの建物が建っている土地の固定資産税や都市計画税額は、住宅用地の特例によって軽減されます。
<住宅用地の特例措置>
| 区分 | 区分詳細 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|---|
| 更地 | 自宅や賃貸アパートなどの建物なし | 課税標準額×1.4% | 課税標準額×0.3% |
| 小規模宅地 | 住宅用地で住戸1戸につき200㎡までの部分 | 課税標準額×1/6×1.4% | 課税標準額×1/3×0.3% |
| 一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地(200㎡を超えた部分) | 課税標準額×1/3×1.4% | 課税標準額×2/3×0.3% |
建物を解体して更地にしてしまうと軽減措置は受けられなくなってしまい、土地の固定資産税・都市計画税が高くなります。
なお、空き家等対策特別措置法により、自治体に「特定空き家」に指定された場合も、固定資産税の軽減措置が適用されなくなります。
固定資産税や都市計画税が課されるのは「その年の1月1日に不動産を所有していた人」なので、売却活動が長引いて年をまたぐと高額な税金がかかってしまう可能性があります。解体してから売るなら、年をまたがず、なるべく早く売った方がよいでしょう。
再建築不可物件だと建物を新築できない
土地によっては「建物を再建築できない場所」があります。
再建築できない場所にある物件を「再建築不可物件」といいます。建物を建てた時点では法律違反ではなかったけれど、その後の法整備によって違法状態となってしまったものです。
具体的には「建築基準法の接道義務」を満たしていないために再建築が認められないケースが多くなっています。
建築基準法により、建物を建てるためには敷地が「幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2m以上接している」必要があります(接道義務)。
接道義務を満たさない土地上の建物をいったん解体すると、新しく建物を建てることはできません。建物を維持したいならリフォームやリノベーションによって対応するしかありません。
再建築不可物件は「土地」としてしか活用できないので極めて低い価額でしか売れないケースも多々あります。
建物を新築できない土地であれば、建物を解体しない方がよいでしょう。
なお再建築不可物件は、たいへん売却の難しい不動産ですが、売る方法がないわけでありません。売却を検討中の方は、下記記事もご確認ください。

既存不適格物件の場合、建て替えに制限がかかる
建物が「既存不適格物件」に該当する場合にも、解体には注意が必要です。
既存不適格物件とは、新築時には適法に建てられた建物であっても、その後の法令の改正や都市計画の変更などにより、現在の法令によると違法・不適格な部分が生じてしまった物件をいいます。
現在建っている建物にそのまま居住することはできますが、いったん取り壊すと同じ建物は建築できません。新しく建築する建物は現在の法令を遵守した範囲のものに限定されます。
- 建て替える前と同じ延床面積の建物を建てられない
- 同じ用途の建物が建てられない
こういったリスクが発生し、買い手側も購入を躊躇する可能性が高いですし、値下げを要求されるケースも多々あります。
既存不適格物件の場合にも、安易に解体をせず買い手を探してから対応を相談した方がよいでしょう。
買い手が住宅ローン、住宅ローン控除を受けられない可能性がある
住宅ローンは基本的に「住居を購入」するための融資なので、建物がなければ審査に通りにくくなります。
建物を建築する具体的な予定があれば通りますが、建築プランが未定な場合や実現可能性がないとみなされると、融資を拒否されるかもしれません。
また土地だけを先に購入すると、一定期間内に建物を建築しないと「住宅ローン減税」も受けられず、買い手が不利益を受ける可能性があります。
ゆっくりと建築計画について検討する余裕がなくなるため、購入を敬遠されるリスクが発生します。
古家を希望する買主を逃してしまう
古家は所有者にとって価値がなくても、購入者にとっては高い価値を持つケースもよくあります。
特に以下のような物件は人気です。
- 現代の建築様式とは異なる古い方式で建てられている建物
- 古民家風の建物
買主が古家ごと買い取ってDIYをしたり、自分の好みでリフォームしたりして居住する方法が流行しています。地方移住やスローライフに憧れる人が増えているので、所有者にしてみると思ってもみないような古家の需要も高まっているのです。
所有者の自己判断で解体してしまったら、こういった買い手を逃してしまうことになるでしょう。解体前に、エリアごとの古民家需要などを調べてみるようおすすめします。
建物解体をおすすめするタイプ
建物を解体してから売る方法をおすすめできるのは、以下のような状況の方です。
- 建物管理にかかる労力や費用が負担になっている
- 家が古すぎて倒壊寸前など、居住は不可能な状態
- 解体したらすぐに売り出して年内に売却できる予定
- 解体費用を負担してでも、土地を高めに売りたい
- 解体費用を負担する資金がある
- 譲渡所得税が高額になる予定なので節税したい
建物解体をおすすめしないタイプ
建物をすぐに解体せず、不動産業者や買い手候補と相談した方が良いのは以下のような方です。
- 古民家風の建物、昔の建築様式の建物が建っている
- 地方移住の人気エリア
- 再建築不可物件や既存不適格物件が建っている
- 建物の管理はそこまで負担になっていない
- 周辺環境を悪化させる状態ではない
- 解体費用を負担するお金がない
- 多少安くなっても手間や時間をかけずに早く売りたい
家を解体するとデメリットもあるので要確認!

土地上に古家が建っていると「解体しようか」と考えてしまいがちですが、解体にはデメリットも多々あります。新築できない土地や建物の種類が制限される土地もあるので、事前に必ず法令上の制限などを確認しておかねばなりません。
売却活動が長引くと固定資産税の負担が高額になる可能性もありますし、解体工事費を含めた資金計画も必要です。事前に今回お伝えしたメリットやデメリットを踏まえ、すべての要素を確認しておきましょう。
参考【無料】解体工事の一括見積サイト >
一方で更地にしない場合、建物を適切に管理しなければ「特定空き家」に指定されたり周辺住民から苦情が来たりする可能性もあります。放置しないよう注意しましょう。
解体工事費の把握が重要
建物の解体を検討するなら、まずは解体費用がどのくらいかかるのか把握すべきです。
解体費用が意外と安ければ負担も軽いので売却前に解体しやすいですし、予想外に高額な場合は買い手と相談した方が両者のためになります。
解体工事費は、依頼する業者によっても大きく変わるケースが多々あります。複数社に見積もりをとると良い業者を選定しやすいので、解体一括査定を利用しましょう。
以上、家を解体する8つのメリットと7つのデメリット、状況別の対処方法を解説… でした。
参考
古家付き土地をどうやって売ったらいいのか知りたい…という方は下記記事も参考に。古家付きの土地は3つの売却方法があります。それぞれのメリットやデメリットなど、詳しく解説しています。

不動産一括査定サービスの利用も忘れずに!
価格査定と不動産会社探しには、複数の会社にいっぺんに査定依頼できる不動産一括査定サービスが便利。今や不動産や自動車の売却には一括査定サービスを使うのが常識です。一般的な家や土地なら、大手不動産ポータルサイトのHOME4U不動産売却