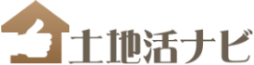「雨漏りしている家を売却するにはどうしたらいいんだろう?」
「修繕しないと売れないのだろうか?そのまま売る方法はあるの?」
「売却手続きの際に何か注意点はないの?買主にどのように説明すればよいのか知りたい」
それなりに築年数の経った家だと雨漏りしていることもありますよね。売却を検討する際には気になるところでしょう。家の買い手は通常、さまざまな部分にまで気を配っています。雨漏りの形跡があれば見逃さないでしょう。
あなたは売主として、その事実と対策を誠実に買い手に伝える必要があるのです。雨漏りを隠して売却すると、損害賠償請求や契約の解除などをされる法的リスクも発生します。
なお雨漏りを隠して売却したときの責任は、民法改正によって「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わっています。

そこで今回は、雨漏りしている家を売却するために注意するべきポイントと具体的な売却方法を5つご紹介します。ひとつ間違えると責任を問われて大きなトラブルに巻き込まれることもありますので、確認する前に売却を進めないでください。
最後までお読みいただければ、「雨漏りしている家」を売却する際にどのような対策をすれば安全かつスムーズに売れるのか、理解していただけますよ。
雨漏りとは?

「雨漏り」とは具体的にどのような状態のことを指すのでしょうか?
端的にいうと、雨漏りとは雨水が建物の内部に侵入することをいいます。多くの場合、建物の老朽化や不具合による屋根や外壁などの防水塗膜の劣化、ひび割れ、剥がれ、穴あきなどが原因となります。
その他、ベランダやバルコニーの防水の劣化やひび割れ、穴あきによって雨水が回ってきてしまい、階下に雨漏りが発生することもあります。
建物内部に浸水していればすぐに修理しないと住めなくなるでしょう。浸水が起こっていない場合でも、ひび割れなどをそのままにしておくと躯体内部で腐食やシロアリ被害が進むなど、建物自体の劣化を早めてしまう可能性があります。

雨漏りの痕跡があるなら、できるだけ早く専門業者などに調査を依頼しましょう。
なお雨漏りの形跡は天気が良くなると乾いて消えてしまうこともありますが、侵入経路は残っています。雨漏りが発生した場合には、デジカメやスマートフォンで写真を撮って現象を記録しておきましょう。
雨漏りが発生している家を売却する際には告知義務あり

ここでは、雨漏りの告知義務と「契約不適合責任」について説明します。なお売主の責任は2020年4月の民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更されています。法的な話で少し難解ですが、大事なことなのでよく確認してください。
雨漏りの告知義務
雨漏りが発生している家を売却する場合、売主はその事実を買主に対して告知する義務があります。
「付帯設備表及び物件状況等報告書」に記載して、買主へ告知するのが一般的です。
<物件状況等報告書の例>

これにより、買主は雨漏りの事実を知った上でその物件を購入することとなります。実務的には、媒介契約を締結する段階で不動産業者に告知しておくとよいでしょう。
契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売買の目的物が契約の目的に合致しないときに売主が負う責任です。家に雨漏りが発生していると、通常「居住する」という契約の目的に合致しません。
そこで雨漏りを告知せずに売ると、後に買主から「契約不適合責任」を追求される可能性があります。契約不適合責任は「買主が欠陥を知っている場合」にも発生するので注意が必要です。
雨漏り以外にもシロアリ被害や給排水管の故障・建物の重要な構造部の欠陥、腐食・地中埋設物などの問題があれば、必ず相手に告知しなければなりません。
雨漏りが発生していると、カビやシロアリなどのリスクも高まります。雨漏り以外にも、こういった二次被害が発生している場合には、買主へすべて告知しなければなりません。
契約不適合責任が発生した場合の効果
契約不適合責任が発生すると、買主から以下のような請求をされる可能性があります。
- 修理請求、代替物の引き渡し請求
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約の解除
それぞれについて解説します。
修理請求、代替物の引き渡し請求
まずは物件の修理を求められる可能性が濃厚です。法律上は「代替物(代わりの物件)の請求も可能ですが、不動産の場合、代替物は考えにくいので代替物請求をされる可能性はほとんどないでしょう。
代金減額請求
修理請求に応じない場合、雨漏りの程度に応じて売買代金の減額請求をされる可能性があります。
損害賠償請求
雨漏りによって買主に発生した損害の賠償請求をされる可能性があります。損害額は予想外に高額になるケースもあり、軽く考えてはなりません。
契約の解除
買主が売主へ修理請求を行っても対応しなければ、最終的に売買契約を解除される可能性もあります。
契約不適合責任の期間は「買主が契約不適合を知ってから1年」ですが、特約によって短くしたり免責したりできます。個人間売買の場合、期間を「引き渡し後2~3ヶ月程度」に限定するケースが多数です。
なお2020年3月までの旧民法では契約不適合責任ではなく「瑕疵担保責任」という責任が規定されていたので「瑕疵担保責任」になじみのある方もおられるでしょう。しかし2020年4月以降の契約では「契約不適合責任」が適用されるので注意してください。
契約不適合責任が免責されるケースと免責できないケース
買主が不動産会社などの宅建業者の場合、一般的に契約不適合責任を免責するケースが多数です。プロである以上、売主の責任を残す必要がないからです。
また、個人間売買でも建物が老朽化して使用できない状態になっている場合は、契約不適合責任を免責して取引することもあります。
一方、売主が不動産会社などの宅建業者の場合、契約不適合責任を免除できません。最低2年は契約不適合責任の期間が発生します。新築住宅の場合も同様です。
契約不適合責任は「売主が契約不適合」を知っていても発生するので、告知したからといって免れるわけではありません。契約不適合責任の発生期間内に生じた雨漏りに関しては責任を負う必要があり、修理などの対応をしなければなりません。
しかし告知しなければ、後に大幅な代金減額や高額な損害賠償請求をされる危険が高まります。雨漏りをしているなら、必ず告知したうえで雨漏りを前提とした売買条件を定めて契約書にも書き入れておきましょう。
個人が売主の場合、きちんと「告知義務」を果たしていれば、契約で定めた契約不適合責任の期間を過ぎれば責任を免れます。
契約不適合責任免責でも告知しないと損害賠償請求リスクあり!
売主の契約不適合責任に関する民法の規定は任意規定です。契約自由の原則により、これらの規定と異なる特約をすることも契約当事者(売主と買主)が納得していれば可能です。
そのため、民法では契約不適合責任の期間が「瑕疵を発見した時から1年以内」とされていますが、一般的な中古住宅の売買契約では契約不適合責任の発生期間を2~3ヶ月としたり、免除したりすることもよくあります。
つまり、中古物件の個人間売買では、契約不適合責任を免責して「売主が契約不適合責任を負わない」 契約も、買主が合意すれば締結できます。
ただし、売主が契約不適合の事実を知りながら買主にそれを告げていなかった場合は、告知義務を果たしていないことから、契約不適合責任を免責とする合意は無効となります。
修理請求、契約解除や損害賠償請求のリスクが発生するので、くれぐれも「雨漏りの事実」を隠さないよう注意しましょう。
新築住宅の場合は「品確法」の瑕疵担保責任が適用される
2000年に施行された「住宅の品質確保の促進に関する法律」(通称:品確法)では、不動産会社や施工会社が新築住宅を販売したときの「瑕疵担保責任」を定めています。
瑕疵担保責任とは「目的物に欠陥や傷があったときに売主が負う責任」です。契約不適合責任とよく似たものと理解しましょう。雨漏りやシロアリ被害、カビなどの欠陥も品確法の「瑕疵」に該当します。
また品確法によると、新築住宅の建築販売において瑕疵があった場合の瑕疵担保責任は「10年間存続する」と定めています。
したがって、新築住宅を購入した場合には、10年以内であれば雨漏りが発生したときに、買主は品確法によって売主へ解除や損害賠償請求ができます。
品確法にもとづく瑕疵担保責任は特約によっても免除できません。
雨漏りしている家を売却する5つの方法

雨漏りしている家を売却する方法として、次の5つが考えられます。
- 現況のまま修繕費用分を値引きして売却
- 修繕してから売却
- 建物の取り壊し、建替えを前提に「現況有姿」で売却
- 解体して更地として売却
- 専門の不動産買取業者へ売却
それぞれの方法についてメリット・デメリットをまとめた表がこちらです。
| 売却方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現況のまま修繕費用分を値引きして売却 | ・買い手が施工業者を選ぶことができる ・修繕の手間がかからない ・すぐに売却できる | 買い手が物件に対してネガティブなイメージを持ってしまうリスクがある |
| 修繕してから売却 | ・高く売却できる ・買い手が物件に対してネガティブなイメージを持たない ・買い手に安心感を与えられる | ・工事費用が発生する ・工事の手間がかかる ・すぐには売却できない |
| 建物の取り壊し、建替えを前提に「現況有姿」で売却 | 売主の手間が一切かからない | ・価格を下げないと売れない ・見た目が悪いので、個人客には敬遠されがち |
| 解体して更地として売却 | ・見た目もスッキリして売りやすくなる ・建物の管理や建物に対する瑕疵担保責任も必要ない | ・解体費用がかかる ・売れ残った場合は翌年の固定資産税・都市計画税が高くなる(軽減措置を受けられないため) ・建物の滅失登記をしなければならない |
| 専門の不動産買取業者へ売却 | ・すぐに売却できる ・手間がかからない ・契約不適合責任を負わずにすみ、安心して売却できる | 売却費用が安くなる |
以下に詳しく説明します。
現況のまま修繕費用分を値引きして売却
雨漏りの問題があることを告知したうえで、修繕費用を見積もり値引きして売却する方法です。建物が今後も利用できる状態で、雨漏りの他に重大な瑕疵がないケースに適します。
修繕費用額は建物の規模、構造、雨漏りの状況や発生箇所数などによって変わります。雨漏りだけではなくカビの除去やシロアリ駆除などが必要になるケースもあります。
契約締結前に雨漏りの原因や発生箇所を特定し、修繕の施工内容や施工方法などについて買い手と合意して修繕費用を算定しましょう。
買い手が工事内容に納得し、合意形成ができていれば後々のトラブルに発展しにくくなります。
主導的に修繕工事を行いたい買い手も多いので、この方法が最近の主流となっています。
この方法のメリットは以下の通りです。
- 買い手が施工業者を選ぶことができる
- すぐに売却できる
売主が修繕工事を発注したり完了を確認したりする必要がなく、手間がかかりません。
現状のまますぐに売却できるので、急いでいるときでもすぐに売却できるメリットがあります。
デメリットとしては、買い手が「雨漏りの他にも何か不具合があるのではないか・・・」と、他の欠陥についても疑心暗鬼になり、
- 物件に対してネガティブなイメージを持ってしまうリスクがある
ことです。
売主として積極的に情報開示などをして、そういったイメージを持たれないよう、じゅうぶんな注意が必要です。
- 売主が急な転勤などで引渡しまでの時間的猶予がない
- 買主が主体的に修繕を行いたいと望んでいる
- 修繕の手間をかけたくない
修繕してから売却
高く売却できるのは、この方法です。
「現況のまま修繕費用分を値引きして売却」しても「修繕してから売却」しても、修繕費分は差し引かれるため、どちらも同じように考える方もおられるでしょう。しかし、修繕してから売却した方が物件に対してネガティブなイメージを持たれないメリットがあります。
また、修繕費用がどのくらいかかるのか予想がつかない物件は購入しにくいため、買い手から敬遠されがちです。修繕が終了していたら買い手が安心できるので、売りやすくなるメリットもあります。
施工業者の選定は慎重に!
ただし、施工業者の選定には注意が必要です。業者によっては非常に高額な費用や次々に追加費用がかかったり、施工時期が遅れるなど誠実に対応してもらえなかったりするケースがあります。
事前に、雨漏りの発生状況や発生場所の特定、再現調査、物件の引渡し前調査、工事状況写真の提出、保証書発行などの手段を尽くし、誠実で信頼のおける施工業者を選びましょう。
その際には「タウンライフリフォーム(外壁・屋根)無料一括見積り」のようなサービスを利用して、必ず複数の施工業者から見積り書や工事提案書を受けるようにしてください。
見積り依頼には複数業者からいっぺんに査定価格を集めて比較できる「一括査定サイト」を利用すると便利なので、最近では利用する方が増えています。
修繕してから売却するメリットとしては、このようなものが挙げられます。
- 高く売却できる
- 買い手が物件に対してネガティブなイメージを持たない
- 買い手に安心感を与えられる
などがあります。
デメリットは以下の3点です。
- 工事費用がかかる
- すぐには売却できない
- 修繕の手間が発生する
雨漏りの原因がコーキング補修など簡易的な作業で済む場合は、工事費も数万円から10万円程度の軽微なもので済むケースが多数です。
一方、経年劣化などによって大規模な補修が必要となる場合やシロアリ駆除などの二次被害が広範囲で発生している場合などには、100万円単位の費用が発生する可能性もあります。
築年数の古い物件に高額な修理費用をかけるより、解体して更地で売却した方が経済的なケースも少なくありません。修繕して売却する方法を選択する場合は、事前に工事費用の見積もりをしっかりとって、修繕するかそのまま売るか更地にするか総合的に検討しましょう。
- 多少の手間をかけても高く売りたい
- 修繕部分が軽微であまり費用がかからない
建物の取り壊しを前提に「現況有姿」で売却
建物は取り壊すことを前提に、雨漏りをそのままにして現況有姿で売却する方法です。この方法のメリットは売主の手間が一切かからないことです。
築年数の非常に古いボロボロ物件で、これ以上利用できない場合などに適しています。
「現況のまま修繕費用分を値引きして売却」との違いは、建物を取り壊す前提なので「修繕」を前提としないことです。現況有姿方式では、修繕費用の見積りも取りませんし修繕費用の値引きもしません。はじめから解体を想定した低額な費用を設定します。
こういったケースでは雨漏りを告知した上で「現況有姿・契約不適合責任免責」として売却するとよいでしょう。
立地やエリアさえ問題なければ、建て替え前提物件として売却できる可能性が高くなります。
デメリットとしては、
- 価格を下げないと売れない
- 見た目が悪いので、個人客には敬遠されがち
などがあります。
- 物件の老朽化や雨漏りなどの傷みが激しく、修繕すると過大な費用がかかってしまう
- 買主も売主も「建物の取り壊し」を望んでいる
解体して更地として売却
ボロボロの建物が建っている場合には、自分で解体して更地にしてから売却する方法があります。更地の方が見た目もスッキリして売りやすくなり、建物の管理や雨漏りなどに関する契約不適合責任の心配もなくなります。
ただし、建物が建築基準法の接道要件を満たしていない「再建築不可物件」の場合、解体してしまうと土地上に新しく建物を建てることができません。その場合、事前に買主へ告知しておく必要があります。
再建築不可物件の売却方法に関しては、下記記事にて詳しく解説しています。

解体してから売却する方法のデメリットは以下の通りです。
- 解体費用がかかる
- 売れ残った場合は翌年の固定資産税・都市計画税が高くなる(軽減措置を受けられないため)
- 建物の滅失登記をしなければならない
とくに、解体費用は非常に高額になる可能性があるので要注意!
木造住宅の場合、@3万円~4万円/坪が目安で、一戸建てを解体する場合には100万円以上の費用がかかるケースもあります。
解体工事の坪当たり単価の相場はこちらを参考にしてください。
<解体工事の費用相場>
| 構造 | 坪当たりの単価 |
|---|---|
| 木造 | 3万円~4万円 |
| 鉄骨造 | 4万円~5万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 5万円~8万円 |
解体工事の費用相場は 万円 〜 万円です。
土地の売却代金を原資として解体費用を支払うことができればよいのですが、そうはいかないため事前に資金計画をしっかりと立てておきましょう。
参考【無料】解体工事の一括見積サイト >
- 物件が老朽化して傷みが激しく、修繕すると多額の費用がかかる
- 時間や解体費用に充てる資金に余裕がある
専門の不動産買取業者へ売却
5つ目に、雨漏りしている物件を残したまま専門の不動産買取業者へ売却する方法があります。
不動産会社の中には老朽化した建物が建っている土地などの「訳あり物件」を専門的に取り扱っている業者があります。そういった業者を探して売却を打診すると、すぐに見積もりを出してもらえて売却できます。
メリットは以下の通りです。
- すぐに売却できる
- 手間がかからない
- 契約不適合責任を負わずにすみ、安心して売却できる
この方法であれば、自分で修繕や解体をしなくて良いので手間や費用がかかりません。建物の見た目が悪くても、相手は専門業者なので買い取ってくれます。
雨漏りだけではなくシロアリやカビなどの二次被害が発生している傷みの激しい物件が建っていても売却可能です。相手がプロなので契約不適合責任を完全に免責できて、後に責任追及されるリスクも発生しません。
デメリットは
- 売却価額が低くなる
ことです。
専門の買取業者に売却する場合、相場価格の7割程度の買取価額になるケースが多数です。
- 買主を見つけるのが手間になる
- 物件がボロボロで買主が見つからない
- 多少売却価額が低くなってもかまわない
- 早く売却したい
- 契約不適合責任を負わず安全に売却したい
家の売却の際には「雨漏り」を必ず伝えよう
雨漏りしている家の売却を検討するとき、いきなり修理に取りかかるのはお勧めしません。まずは雨漏りの程度や建物の築年数、修理にかかる費用感などを確認しましょう。
買主に修繕を託した方が適切なケースも多々あります。売却を急いでいるのか時間をかけてもかまわないのかなども勘案して戦略を立てましょう。
また告知義務は極めて重要です。媒介を依頼した不動産業者や買い手候補に雨漏りの事実を伝えることは必須です。
高く売りたいがために、事実を隠ぺいするようなことはあってはいけません。
後になって発覚し、買い手や不動産業者との信頼関係を壊すことになって大きなトラブルにつながります。契約解除や高額な損害賠償請求をされ、最終的に裁判を起こされるリスクも発生します。
付帯設備表や物件状況等報告書などを利用して、雨漏りの事実や対応策について不動産業者や買い手と共有しましょう。
以上、雨漏りしている家を売却する5つの方法と注意点をお伝えしました。
参考
雨漏りが激しくて再建築不可物件でも売却できる不動産業者を探したい…という方は下記記事も参考に。一括査定サイトを利用すると、そのような業者が見つかる可能性も高くなりますよ。

不動産一括査定サービスの利用も忘れずに!
価格査定と不動産会社探しには、複数の会社にいっぺんに査定依頼できる不動産一括査定サービスが便利。今や不動産や自動車の売却には一括査定サービスを使うのが常識です。一般的な家や土地なら、大手不動産ポータルサイトのHOME4U不動産売却