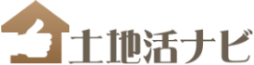サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の経営に関して・・・
「今後さらに高齢化が進んで、引っ張りだこになるはず!」
「国が積極的に増やそうとしている施設だから、間違いないだろう!」
そんなふうに安易に考えてはいませんか?
もちろん、そういったメリットがないわけではありませんが、必ず成功が約束された土地活用なんてありません。とくにサ高住は運営形態として特殊な点が多く、アパートや老人ホームとは似て非なるものです。
そこで今回は、土地活用としてサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を経営することのメリットとデメリットを解説します。
サ高住経営を検討中の方は、ぜひご一読ください。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは?
サ高住とは、おも に民間企業が運営する介護施設のことで、その名の通り「サービスが付いている高齢者向けの住居」になります。
高齢化が進む中で、特別養護施設などの公的な施設が不足しているため、民間企業が運営するサ高住に注目が集まっています 。
ただし、通常のサ高住である、いわゆる「一般型」のサ高住は、「介護が必要でない比較的元気な高齢者」を対象としているため、自分1人で立てなかったり、食事が自分でできなかったりする高齢者は対象外になります。
たとえば、介護が必要な方を受け入れる老人ホームなどは、入浴や排せつなどの介助、健康管理などが義務付けられています。一方、サ高住は「安否確認」と「生活相談」の2つしか義務付けられていません 。
そのため、ひとりで自宅にいるのは不安だが介護は必要ない層が利用する施設がサ高住となります。
サ高住の家賃相場

サ高住の家賃相場ですが、通常の「一般型」の場合、近隣の賃貸住宅の家賃相場に合わせるケースが多いようです。
なお、サ高住では安否確認と生活相談が必須サービスなので、この費用を管理費に含めたり、別途サービス費として徴収しています。
「介護型」の場合、これに食事サービスが加わるので、さらに費用がかかります。おおよそ「一般型」に10~15万円ほど上乗せされるケースが多いようです。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を経営するメリット

次に、 サ高住を経営するメリットを解説します 。サ高住は、ターゲットを高齢者と限定していることによる、ほかの土地活用とは違ったメリットがあります。
- 高齢化社会の進展による入居ニーズの高まり
- 立地の影響を受けにくい
- 一定基準を満たして登録すると補助金がもらえる
- 一定基準を満たして登録すると税制優遇がある
- 地域社会に貢献できる
それぞれについて、順に見ていきましょう。
高齢化社会の進展による入居ニーズの高まり
まず、そもそもサ高住ができた背景でもある「高齢化社会によるニーズの高まり」という点がメリットとして挙げられます。内閣府のデータ※によると、日本の高齢者(65歳以上)の人数と構成比は年々増加していくことが予測されます。
| 年 | 高齢者(65歳以上)の人数 | 全人口 | 高齢者の構成比 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 3,395万人 | 12,660万人 | 26.8% |
| 2020年 | 3,612万人 | 12,410万人 | 29.1% |
| 2025年 | 3,658万人 | 12,066万人 | 30.3% |
| 2030年 | 3,685万人 | 11,662万人 | 31.6% |
| 2035年 | 3,740万人 | 11,212万人 | 33.4% |
| 2040年 | 3,868万人 | 10,728万人 | 36.1% |
| 2045年 | 3,857万人 | 10,221万人 | 37.7% |
| 2050年 | 3,768万人 | 9,708万人 | 38.8% |
2025年には65歳以上の高齢者の構成比は30%を超え、2035年には3人に1人が高齢者です。さらに、出生率が上がらない限りは、高齢者の人口が横ばいでも高齢者の構成比は高くなり続けます。
今でさえ介護施設が不足しているのですから、今後サ高住へのニーズはますます高まっていくでしょう。
※引用元:内閣府 将来推計人口でみる50年後の日本
立地の影響を受けにくい
たとえば、賃貸マンションの場合 、駅や商業施設が遠かったりすると、人気が落ちるとともに家賃相場も下がります。
いっぽう、サ高住では利便性の低い立地でも経営が成り立ちます。
というのも、サ高住に居住する高齢者は、日常的に駅を利用するわけでもなく、頻繁に出かけることも多くありません。
そのため、必ずしも駅近だったり商業施設が目の前にある必要はないのです。
通常、立地条件は家賃相場に大きな影響を与えます。
もちろん、サ高住の場合も、お見舞いに行きやすいという点では立地が良いに越したことはありません。
とはいえ、一般的な賃貸経営に比べると立地のハードルは低いといえるでしょう。
一定基準を満たして登録すると補助金がもらえる
サ高住は、国として必要な施設なので、以下の要件をクリアしていれば国から補助金がもらえます。
- サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅
- サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録する
- 入居者の家賃の額が周辺と比較して不均衡でない
- 事業の資金の調達が確実である
- 家賃の徴収が前払いと限定しないこと
- 地元市区町村の意見で街づくりに支障がないもの
「サービス付き高齢者向け住宅として登録」に関しては、バリアフリーなどサ高住としての機能を備えていることが前提条件です。
上記に該当するサ高住は、補助金として新築工事は工事費の1/10以内、建物改修の場合は工事費の1/3以内が支給されます。また、新築は1住戸120万円以内、改修 は1住戸150万円以内という上限設定もあります。
一定基準を満たして登録すると税制優遇がある
また、サ高住には固定資産税と不動産取得税の優遇もあります。固定資産税とは、不動産の所有者に毎年課せられる税金で、不動産取得税は不動産を取得したとき1度だけかかる税金です。
以下の要件に当てはまるサ高住は、税金の優遇措置があります。
- 床面積が30㎡以上/戸
- 個数が10戸以上
- 前項の補助金に該当する
- 需要構造部分が耐火もしくは準耐火構造
固定資産税は、1/2以上5/6以下の範囲において税金が軽減されます 。また、不動産取得税は、家屋の部分は 課税標準額から1,200万円控除されます。
土地部分も「家屋の床面積の2倍にあたる面積を課税される土地面積から差し引く」という軽減措置があります。つまり、課税対象の土地面積が小さくなる分、税金が安くなります 。
地域社会に貢献できる
サ高住は地域社会に貢献できるというメリットもあります。 高齢化社会が進むにつれて 、施設に入りたいけど入れない方は増えていくことが予想されます。
そんな中、近所でサ高住ができたら、サ高住に入居する本人だけでなく家族にとっても嬉しいことでしょう 。
通常の賃貸経営に比べると、サ高住経営は地域社会への貢献度が高い土地活用といえます。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を経営するデメリットとリスク

サ高住の経営にはデメリットやリスクもあります。経営を始める前に必ず確認しておきましょう。
- サービス施設や共用部分の比率が高く、ある程度広い土地が必要
- サービス施設にお金がかかり、坪単価は高くなる
- 敷地の収益効率は低く、利回りはアパートやマンションに劣る
- サービス事業者の質によって経営が大きく左右される
- サービス事業者が中途解約するリスクがある
- 介護保険の負担増を避けるため、開発規制をかけている自治体も
- 国の制度改正などにより補助金が増減するおそれがある
- 高齢入居者が入院したり亡くなったりすることによる退去
- 建物が特殊なので転用性が極めて低い
それぞれについて、以下に詳しく解説します。
サービス施設や共用部分の比率が高く、ある程度広い土地が必要
サ高住は、共用施設や水回りを一般の住居よりも広く設計する必要があります。たとえば、廊下や浴室、トイレなどは車いすが入れるスペースが必要です。
また、サ高住の住民が全員で利用できる多目的室や食堂など、通常の住居では必要のない共用部もつくります。
戸数が同じでも、サ高住は賃貸マンションより広い床面積が必要です。したがって、ある程度広い土地がないと建築できません。
サービス施設にお金がかかり、坪単価は高くなる
サ高住にはさまざまま共用部が必要な上、トイレや浴室などの設備・仕様も高齢者向けに作らなければなりません。
その分、建築費の坪単価は高くなります。
敷地の収益効率は低く、利回りはアパートやマンションに劣る
基本的にサ高住の利回りは、以下の理由によりアパート経営やマンション経営に劣ります。
- 建築費が高くなる
- 同じ土地でも戸数が少ない
- 設備のメンテナンス 費用が高額になる
サ高住の家賃は通常の賃貸マンションより高く設定できるとはいえ、初期費用やメンテナンス等のランニングコストも高く、住戸数が少ないので、利回りは低くなりがちです。
サ高住に限らず、土地活用の際に必ず理解しておきたいのが「利回り」です。利回りは重要な指標ですが、利回りの高さだけで判断することにも大きな落とし穴があります。詳しくは↓の記事をご確認ください。

サービス事業者の質によって経営が大きく左右される
一般型のサ高住は安否確認と生活相談のふたつが義務付けられています。
具体的には、スタッフが定期的に室内を訪問して安否確認したり、居住者が困っていることを助けたりします。
そのため、サ高住には一定数のスタッフが必要になります。また、スタッフが不在の夜間でも緊急通報に対応できるような態勢を整えておく必要があるでしょう。
サ高住の運営は 外部のサービス事業者に依頼しますが、そのサービス事業者の質が悪ければ入居者からの評判も悪くなります。
そうなると、空室が増えて経営が成り立たなくなってしまうかもしれません。
ところが、このような場合でも経営者にできることはほとんどありません。
サービス事業者の質によって経営が大きく左右されてしまう点は、サ高住経営のデメリットといえるでしょう。
サービス事業者が中途解約するリスクがある
サービス事業者は、賃貸マンション経営の管理会社のような存在ですが、サービス事業者側から中途解約されることもあります。
通常の賃貸物件と違って、介護の資格や経験をもったスタッフが必要になるので、人員確保が難しいことも要因のひとつです。
もちろん契約がある以上「明日からもう来ません」ということはないでしょうが、それでも「一ヶ月後に解約」となれば、急ぎ後任のサービス事業者を探さなければなりません。
契約相手が変わればサービスの委託料も違いますので事業収支は大きく影響を受けるかもしれません。また、入居者も新しいスタッフと一から関係性を築く必要があるので、なんらかの軋轢や不満が生じる可能性もあるでしょう。
介護保険の負担増を避けるため、開発規制をかけている自治体も
自治体によっては、サ高住の建築ができないよう開発に規制をかけているところもあります。開発規制をかけている一番の理由は、サ高住は「住所地特例」が使えないからです。
たとえば、荒川区に住んでいた人が、練馬区の介護施設に入るとします。仮に、住所地特例が使えれば、元々住んでいた荒川区が介護保険の負担をします。
しかし、サ高住は住所地特例が使えないので、サ高住を建築した自治体が介護保険を支払わなければなりません 。
介護保険が自治体財政を圧迫することのないよう 開発規制をかけてサ高住を建築できないようにし、介護保険の支払いを避ける自治体もあります。
国の制度改正などにより補助金が増減するおそれがある
サ高住への補助金や税制優遇は、国の制度改正によっていつ増減するか分かりません。まったく優遇がなくなってしまう可能性もないとはいえないでしょう。
サ高住を始める際には、制度改正による経営環境の変化をあらかじめ想定しておく必要があります。
高齢入居者が入院したり亡くなったりすることによる退去
高齢者のみが入居するサ高住は、通常の賃貸マンションより入居者が入院や亡くなるリスクは高いでしょう。
突然の退去により空室ができると収支計画に狂いが生じてしまいます。
このような空室リスクは、ほかの賃貸経営よりも大きいといえます。
建物が特殊なので転用性が極めて低い
サ高住は建築費が高額なので、回収までに多くの年数が必要になります。
また、他の用途に改修するにも、間取りが特殊で共用施設なども通常の賃貸マンションとは異なるので、多額の改修費用がかかってしまいます。
つまり、転用性の極めて低い土地活用なので、いったん始めたらサ高住経営をずっと行っていくという覚悟が必要です。
高いニーズはあるもののハードルの高いサ高住経営
サ高住経営には多くのメリットともにデメリットやリスクがあることも見逃せません。
立地を選ばない点はメリットですが、賃貸アパートやマンションより経営のハードルは高いといえるでしょう。
とはいえ、急速に高齢化が進む日本社会において、今後ますますニーズが高まっていくことは間違いありません。
サ高住経営を検討する際には、そのメリットやデメリットを他の土地活用と比較してみることをおすすめします。
以上、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)経営を始める前に知っておきたい5つのメリットと9つのデメリット&リスク…でした。
参考記事:
サ高住の資料はどこに請求したらよいか分からない…という方は下記記事も参考に。サ高住に対応した一括資料請求サイトが分かりますよ。